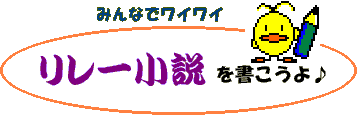|
雨が降った。
悲しくはなかった。寂しさなかった。ただ胸に猫を抱く。猫の体が寒さに震える。信也の体も冷え切っていた。
『そんな野良猫、捨ててきなさい』
『また、そんなもの拾ってきて! うちでは飼えないぞ』
『信也の馬鹿、私が猫嫌いなの知らないの!』
『赤ちゃんもいるんだよ。猫の毛は体に悪いんだよ』
母が父が姉が祖母が責めたてる。信也は猫を抱きしめ、何も考えず抱きしめた。流れる涙。信也の弟......わずか三ヶ月の真司はビックリして泣き出す。
家族達は慌てて、真司をあやしにかかる。
誰も信也の事を見ていない。
信也は黙って、家を出た。誰も信也が出ていった事に気付かない。悲しくなかった。寂しくなかった。ただ猫に囁く。
「僕には君がいるから」
弱々しく鳴く猫。
ずぶ濡れになったまま猫を撫でる。
とその雨が、一時、遮断される。雨は降る。でも、信也には降らない。きょとんとして見上げると、そこには一本の傘が差し出された。にこっと、微笑む女が一人。
「濡れるわよ」
「もう濡れてる」
「もっと濡れるわよ」
「こんなに濡れたら、いくら濡れてもかわらないよ」
「そんなことない。君がよくても猫ちゃんが死んじゃうよ」
「え?」
「私のお家においでよ。坊や、暖かいミルクぐらいあるよ?」
「・・・・・・」
雨が降った。
信也はただ頷いた。
女と一緒にただ歩く。猫は弱々しげに吐息をもらした。
(僕が僕が.....何も考えなかったから)
涙がまた流れる。
女はそっと信也を抱きしめた。
「大丈夫。まだ仔猫だからね、体力はないの。温めてあげれば大丈夫。すぐによくなるからね」
「うん」
泣いた。どれが雨でどれが涙なのか分からないくらい泣いた。そっと手を握ってくれる彼女の温もりが、とても嬉しくて嬉しくて四歳の信也は、はじめて-----やっと、四歳らしい感情を表出できた。信也は寂しくて、ずっと我慢していた。それを家族は気付かなかった。それをこの女は気付いた。それをこの仔猫し理解してくれていた。
「猫ちゃんのミルクもあるからね」
「うん」
何度もうなずく。「うん」
「にゃー」
弱々しく、でも優しく猫も鳴いて、信也の手をざらざらした舌でペロリと舐めた。
「信也!」
雨の音にかき消されて、必死に探す家族の姿に信也はまるで気付かなかった。家族も焦りで、見落としていた。
すれ違って、そのまま消えた。
雨の音に消えた。
淋しさに震えて、信也と猫は寒さに凍えた。
雨は降る...........
|