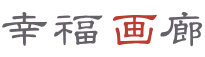
第17話
「 他人の群れ 」
■■プロローグ
華、であった。皆が頭を垂れてひれ伏す中にそれを睥睨
「ダチュラ夫人、いかがですか、久しぶりのこの国は? 懐かしいでしょう?」
「ワタクシがこの国に戻ったのは、郷愁からではありません」
「何カ国をお巡りになっていたんです?」
「それこそ、世界中を」
ダチュラ夫人が艶やかに言う。
キィーっと僅かな音を立てて、サロンに黒服長身の男が入って来た。夫人が視線を向ける。そっと、夫人の口唇に微笑みが浮かんだのはその時だ。なんとも形容しがたいアルカイックスマイル。美しさが更に増す。
「ああ、お久しぶりね、貴方」
「こちらへ」と誘うように、黒いレェスの手袋をつけた手を差し向ける。男がつかつかと歩み寄る。座す夫人の上げられた手を取るとその甲にそっと接吻した。
「髪が伸びたのね、それも似合っていてよ。ワタクシの美しい朱色・ヴァーミリオン」
夫人は懐かしい声音で朱里
■■1
「……チクショウ」
ふるふるとペンを握った拳
「何で警察官の昇級試験科目に外国語なんてあるんだ〜〜〜!?」
そう雄叫びを上げたのは、ダグラス刑事だ。持っていたペンを放り投げると、無精と多忙が重なり合って構築された伸び放題のボサボサ頭をわしゃわしゃとかき乱す。クセのある黒い髪が更にもつれた。
ダグラスは直属上司からの強い薦めで、昇進試験を受けることになったのである。目下、寸暇を惜しんで誠心誠意勉学に勤
「犯罪も年々国際化していますから、当然の成り行きかと思います」
こちらは同じ黒でも、クセのない真っ直ぐな髪の持ち主である朱里が応じる。普段は背の中ほどまで伸ばしたそれを肩口で結わえているが、今は風呂上がりなのか、濡れた頭をタオルでゴシゴシ拭いている。片方の手で床に転がったペンを拾い上げると、ダグラスの鼻先に向けて突き出した。
「幾ら文句を言ったところで、何も解決しませんよ。試験にパスしたければ、さっさと問題を解いて下さい」
正論である。だが、だからこそ腹が立つということもある。案の定ダグラスが吠えついた。
「一日の仕事を終えて帰ってきて、ほっと一息の貴重な一時
「それはこっちの台詞です。昇進試験、ちゃんと受ける気があるんですか? ハナからやる気がないのでしたら私は自室に戻りますが?」
そう言って、頭に掛けたタオルの隙間からジロリと睨み付ける。元が整った顔立ちの朱里だけに、冷ややかな目つきには凄みが混じる。ダグラスがほんの少し鼻白んだ。
「だあってよぉ、まさか外国語があるなんて思わねぇだろー」
「ですから、その弱点克服に私がお付き合いしているんじゃないですか」
折角、まがりなりにも昇進試験を受ける気を起こしたダグラスだったが、試験科目に外国語が入ると知った途端に「俺は止めた」と言い出したのだ。彼の刑事としての才覚を大いに買っている直属上司は困り果てた。それはダグラスの親代わりでもあるセント伯爵の耳にまで届き……そうして、にわか家庭教師の役目が朱里に降って湧く事となったのである。
■
どうにも屁理屈ばかりでやる気皆無の男に、朱里独特の、敵の弱点をピンポイントしたハッパがかかる。
「ああ、嘆かわしい。小鳥さんだって、応援しているんですのに」
「うっ……」
「きっと、今頃は夜食のサンドイッチを用意してくれているんでしょうねぇ。料理ベタの彼女が彼女なりに精一杯の心を尽しているんでしょうに。そんな小鳥さんの心遣いを無にしてしまってもよろしいんですか?」
「ううう〜っ」
ダグラスが昇進試験を受ける気になった背景の一つには、必ずや小鳥の存在もある筈である。顔に似合わず純情なダグラスの弱点をここぞとばかりに突いてやる。片恋男はそれに対して、グルグルだのギリギリだの無精髭面に相応しい野性味溢れた擬音でもって呻っている。
一旦やると宣言した以上大人しくやる気を出せばよいものを、全く困った男である。セント老人も言っていたが、ダグラスのような男を平刑事のままにしておくのは、朱里としても勿体ないと思うのだ。ざっと見たところ、刑法その他語学以外の試験科目については特に勉強するまでもなく合格ラインに達しているというのも、更にその思いに拍車を掛ける。
第一、問題のダグラスの語学力が「からっきし」という訳ではないのである。どちらかと言えばかなり『洒脱』にしゃべれる方だ。ただ、その洒脱ぶりが問題で、これは『達者』とはちょっと違う。実用本位で覚えすぎとでも言うのだろうか、とにかく俗語
「やれば出来る子なのに」などと小学校の先生のような台詞をついつい口走ってみたくなる。言ったが最後、悪童さながら本気でつむじを曲げてしまうのだろうから、そういう訳にも行かないが。よって、別の路線で攻めてみる。
「男なら昇進して多くの部下を従えるというのも、一つのロマンだと思いますがね」
「よっく言うぜ」
ダグラスが反撃してくる。
「お前だって、言っちゃあナンだが、こんなうらぶれた館で白野坊やのお守り役一筋に徹していやがるクセによ!」
朱里の目がスッと細くなった。ダグラスの昇進試験と自分の現状。その間に何の因果関係があると言うのだろう。大いに余計なお世話である。
「私の場合、刑事と違って期待を掛けてくれる上司も、親身になってくれる親代わりもおりませんから」
「その爺さんがな『勿体ない』って言ってたぞ。お前は一介の執事で終わらせていいような玉じゃあねぇってよ」
「私はこの館の執事という職に充分満足しています」
「俺だって、平刑事で大満足なんだよ!」
■
まったく。ああ言えばこう言う。流石に腹が煮えてきた。一発殴ってやろうかと思ったが、衝撃で折角これまでに覚え込ませた正しいスペリングを洗いざらい忘れ去られても業腹である。息を吸い込んで深く吐く。二回繰り返して気を落ち着ける。
「……刑事の場合、昇級には筆記試験にパスするよりも実績評価を上げた方が早そうですが、そういうご予定はないんですか?」
「うーん、連続殺人犯だの、著名人がらみだの、余程大きなヤマを解決せんことにはなぁ」
「難しいですね」
能力よりも運の方が試される選択肢だということだ。かなり望み薄である。
「大体が、殺人なんて物騒なモンは願い下げにしたいしな」
「そうなると……」
ふと、そこでアゴに片手を沿えた姿勢で押し黙った執事に、ダグラスは不穏な空気を感じ取った。こういう時の刑事
「……オマエ、今『いっそ、二階級特進でも狙えばよろしいのに』とか思いやがっただろう」
「そんなまさか。滅相もない」
淀みなく、流れるように返された否定具合が逆にアヤシイ。
「うーそーつーけー」
コンコン、とドアが軽くノックされた。続いてそれがガチャリと開く。
「……あら、筆記科目の特訓だと思ってたけど、実技試験も特訓中なの?」
夜食のサンドイッチとコーヒーを運んできたメイドの小鳥
■■2
「おお、朱里君じゃないか」
ルイス大佐が声をかけてくる。Q紳士倶楽部の談話室である。貴重書の宝庫と言われる著名な社交倶楽部で、紳士と名は付いているが淑女の会員も多い。朱里はクリスマス・プレゼントにセント伯爵からその仮会員証と書庫の鍵を渡されていた(作者注:幸福画廊15)。正式会員に登録されるには、更に五人のメンバーからの承認が必要で、セント老人に紹介されたこのルイス大佐を含め、既に三人が名乗りを上げてくれている。
「また、書庫にお籠もりだったのかね?」
ルイス大佐がご自慢の黒々と蓄えたカイゼル髭を障りながら訊いてくる。朱里が微笑む。
「はい、この書庫にいると、時の経つのを忘れます」
「この倶楽部にはこう言っちゃなんだが、変わり者が多い。キミならさしずめ、ツヴァイクの『書痴
「そのようなことは……。書痴と言われて悪い気は致しません」
「風変わりな絵画ファンも居るしな。彼は画痴
部屋の隅を顎で差す。一人の老人がテーブルの片隅で画集をめくっている。かなり大きな図版である。老人は指で細部をさすりさすり、じっくりと絵を眺めている。このウエストエンド元医師の目がほとんど見えない、というのは周知の事実である。元医師は盲
「宝石や女に目の色を変える者もいるし」
ルイス大佐が二台置かれたビリヤード台を示す。その一方には玉突きに興じる若者達の姿があった。そのうちの金髪の男を目に留めて、朱里が僅かに眉を顰める。
「やぁ、これはこれは朱里じゃないか。キミがこのQ紳士倶楽部に顔を出せるほどのセレブリティになろうとはね。嗤わせてくれるじゃないか。まだ仮会員だったようだが」
「キミもまだ仮会員だろう、ネイサン・ロレーヌ」
金髪の男にルイス大佐が言う。
「ボクには子爵たる父の後押しが付いてますからね、すぐにも正規メンバーです」
「朱里君にもセント伯爵が付いておるよ。キミと違って金の後押しはないようだがね」
キューに付けるチョークを潰す。その手を乱暴にハンカチで拭う。
「失敬な」
「最近、真珠飾りのタイピンやピンブローチが当倶楽部で流行っているようだが」
「アレはボクが正式メンバーになって開くだろう、ボク主催のサロンの通行証のようなものですよ。よろしければルイス大佐にも?」
「結構だよ」
去ろうとする二人を声が追う。
「朱里のようなものと近しくなさらぬ方がいい。御身に傷が付きますよ。セント伯爵をどう丸め込んだのかは知らないが、彼は卑しい召使いの出です。いや、今もそうなんだったよなぁ、朱里」
この名誉あるQ紳士倶楽部へ入り込むなど、身分をわきまえたまえよ。
言いながら、ネイサンがキューで玉を撞く。生憎のミスショットで交代である。
「相変わらず、正確な狙い
それに、ネイサンがカッとなる。
「お前がいるから気が散るんだ。さっさと視界から消えて貰おう」
いいか、言っておく。このQ紳士倶楽部にお前の席などないぞ。ボクがそれを許さない。
■
「Q紳士倶楽部は本来、派閥などというくだらないものを厭う者達の為の倶楽部なんだがね」
故に、変わり者も多いが、穏やかだ。そのようなこの倶楽部が気に入っとるんだが、ロレーヌ子爵は息子育てを誤ったな。ルイス大佐が口髭に手をやりつつ「やれやれ」と言う。
「ああいう手合いこそ、この倶楽部には不向きなのだが」
「私のために失礼致しました」
まぁ、良いさ、と大佐が言う。いろいろおっての社交倶楽部だ。指でさす。
「ほらほら、今度は葉巻の愛好家も」
ガラス張りになった喫煙室では数人の男達が談笑している。誘われて喫煙室に入る。ゆったりとした椅子に腰を下ろす。
「キミ、葉巻は? やってみんかね?」
「私は紙巻き煙草で結構です」
若輩者の執事風情がこのようなお歴々のいる場で葉巻を、というにも不似合いですし、と言うと、ルイス大佐が笑って、差し出したシガーケースを引っ込める。
「そうだ、キミ知っているかね? 明日はこのQ紳士倶楽部で特別なサロンが催される。是非、キミも来るといい。エレガントで気品に満ちたあの夫人は一度は会っておくべき女性
「ご婦人のサロン、ですか?」
淑女会員も居るQ紳士倶楽部とはいえ、女性主催のサロンというのは珍しい筈だ。
「そう、長い渡航から戻られたのだよ、我らが愛すべきダチュラ夫人が」
若いキミでも名前くらい聞いたことはあるだろう? ルイス大佐が紫煙を吐く。
ポトリ、と朱里の手にある煙草から膝に灰がこぼれ落ちる。
「……朱里君?」 もう一度、灰がこぼれ落ちそうになるまでの時間、朱里は黙したままだった。
「……失礼致しました、ルイス大佐」
朱里がこぼれた灰を拾う。
「はい。存じております。華のようなあの方は」
■
「だから、文法とか、意味ワカンネーつってるだろう!」
「意味を見いだして頂けないから、無理矢理丸暗記して貰うしかないんでしょうが」
夜食のサンドイッチとコーヒーを運んできた小鳥が「またやってる」と言う。一緒にとことこ入ってきたこの館の年若き主である白野
「刑事、朱里が鞭を用意しないうちに諦めて覚えた方がイイと思うよ」
「あ、ムチ?」
「朱里が昔いた学校の先生は、出来の悪い生徒の手の甲を乗馬用の鞭で叩いてたんだって」
不出来。朱里が言ったらそのままダグラスと本格バトルになりそうな台詞だが、あっさりと聞き流されてしまうのが、白野の白野たる特権である。
「わ、痛そう」
「執事、よしんばやりやがったら、傷害罪で逮捕だ」
「鞭よりバズーカ砲で撃ちたいです」
「あ?」
「は?」
しばし、男達が睨み合う。
「とにかく、刑事は明日非番でしたでしょう? ですが、私には用事があります。この本のとにかく、ここからここまで、丸暗記しておおきなさい」
白野が軽く小首を傾げる。栗色の巻き毛がふわりと揺れた。
「朱里、明日もまた紳士倶楽部?」
「はい。申し訳ありません、よろしいでしょうか、白野様」
「それは全然イイんだけど」
一年以内に五人のメンバーの推薦が要るんでしょう? 大変そうだもんね。正規メンバーになれたらいいね。白野がそう言って微笑む。
「そんなに本って楽しいの?」普段、雑誌やクロスワードパズルくらいしか本を読まない小鳥が問うた。
■■3
座す夫人の上げられた手を取ると、朱里はその甲にそっと接吻した。
「お久しぶりね、ワタクシの朱色・ヴァーミリオン」
周囲がざわめく。ダチュラ夫人がこれまでに、例えレェスの手袋越しとはいえ、接吻を許した男などいなかった。朱里の長く、肩口で結んだ黒い艶のある髪の毛がサラリと流れる。
「ご無沙汰しておりました、マダム」
「こんな所で会えるなんてね。年若くして名士にお成りになったの、ヴァーミリオン?」
「いえ、私は一介の執事です。セント伯爵のご仲介を頂きましてここに。まだ正式会員でさえないんです」
「そう」
ダチュラ夫人が立ち上がった。
「皆様、お茶を頂きましょう。旅先で出会ったとても美味しい東洋の飲茶
「いや、賑やかなサロンですな」
後ろ髪を引かれる気持ちをこらえて夫人から離れ、立食形式のパーティの、それでも隅に用意された席に座ると、ちょうど隣に腰掛けていたウエストエンド元医師が言ってきた。
「特にダチュラ夫人の声。たとえ目は見えずとも知性、教養、気品、美の滲み出る声というのはあるものなんですなぁ」傍らに寄り添うジョンナーの頭を撫でる。「クーン」と盲導犬が鳴く。
「夫人はいつ頃こちらにお戻りに?」
「もう一年も前だそうですよ。沢山のものを見聞きしてすっかり疲れてしまったからと、社交界からは足が遠ざかっておいでだったそうで」
「左様でしたか」 朱里は手にしたハーブティーを啜る。
「そうだ、朱里君の会員申請証、私も一つお手伝いましょう」
「それは……ありがとうございます」
これで五名中の四名が揃ったことになる。
「いつも、朱里君は私の絵の鑑賞に付き合ってくれるからね」
「私も絵が好きですから」
「君はあの高名な【幸福画廊】の執事だとセント老人から聞いた」
「はい」
「目が見える内に、その絵を一度は見たかったものですなぁ」
【幸福画廊】
その画廊の絵を見ると、人は幸せになるのだと言う。
これまでに味わったことのないような幸福感を得るのだと言う。
その絵を手に入れる為に世の金持達はこぞって大金を積むのだと言う。
全財産を叩いても、惜しくないほどの幸福がその絵の中にはあるのだと言う。
【幸福画廊】
そこは不可思議な人生の一瞬が描かれるところ……。
「はい、本当に」
朱里が淡く微笑んだ。
■
朱里がまだ幼い白野と共にこの国に残されたのは、もう遠い過日だ。
白野の祖母である老婦人の言葉通り、やがて彼らは国外へと去っていき、二人はそのまま取り残された。朱里と白野は、与えられた館でただ二人過ごした。とても穏やかで満ち足りた時間だけが過ぎていく。
「ねぇ、朱里」
「はい?」
呼ばれて答えた。少年が傘の下から、幼い顔を覗かせる。新しく買った傘が余程気に入ったものか、最近は雨の日のたびに外へ出たがる。ポツポツと雨粒が傘に弾ける音が面白いと言う。時々傘をくるんと回すので、隣を歩く朱里の服はいつも飛沫で濡らされる。「こら」と何度叱っても、すぐに忘れてまた繰り返す。
「あのね、僕、働こうと思うんだ」
突然の少年の言葉に、朱里の足が思わず止まる。
「は?」
「だって、朱里はもう僕の執事なんでしょう?」
「そう、ですねぇ」
確かに、最近では家庭教師として彼の勉強を見ている時間より、その身の回りの世話をしている事の方が遙かに多くなってきていた。幼い彼に代わり、屋敷を含めた全ての財産の管理すら当然朱里は任されていたので、既に執事職だと言っても過言ではなかろう。
「だったら、朱里を雇うためにはお金が要るもの。僕が主人なんだから、僕だって働いてなくっちゃあヘンだよね」
「……」
分かったような、全く分からないような理屈だったが、面白いので訊いてみる。
「何をなさって、働かれるおつもりですか?」
「うん。僕、考えたんだけど」
絵を描いて、それを売ることって出来るかな? 僕、まだ小さいし。他に何も出来ないし。みんなに幸せの絵が描けるかな?
かなり真剣な顔付きで訊いてくる。侯爵家から手切れ金として支払われた金は、かなりの額に登っていたので、生涯に渡って白野が喰うに困るハメに陥ることはそうそうなかろうと思われたが、にも関わらず、勤労意欲のあることはとても素晴らしいことである。
それに、と思う。白野の絵が売れたとして、それが彼の自信に繋がるなら、尚更良い。彼の絵はその素晴らしさにも関わらず、これまでずっと否定され続けて来たので。
「ふむ、そうですね。少し考えてみましょうね」
売れる絵、となると、例えば油彩画など学ばせるべきなのだろうか?
絵など、とんと門外漢で、朱里にもすぐには判然としない。
やがて【幸福画廊】という名の館が人々の口に登り始めるまで。
これはそれより少し前の、小さな小さな昔話。
■
その更にずっと前、朱里はロレーヌ子爵邸にあった。ロレーヌ家の執事を務めていた朱里の父と、コックだった母が流行り病で相次いで亡くなってから。まだたった四歳だった朱里は当主のお情けで育てられ、下働きという名目で成長した。朱里よりも二歳年若く子爵家に嫡男として生まれたのがネイサンである。子爵は朱里にネイサンの世話係を命じた。共に行動し、共に教育を受けた。ネイサンに奇矯な振る舞いが見え始めたのはその頃である。
ネイサンは先ず虫に執着した。朱里にトンボや蝶を捕らせ、生きたままその羽を毟る。飛べなくなった虫をアリの巣の上に置いて、虫がアリにたかられていくのをじっと楽しげに眺めている。
馬に乗れる年になると、ウサギ狩りだと称して領地に何頭もの犬を放つ。朱里に一緒に捕まえるよう命じる。
「申し訳ありません、ネイサン様。逃がしてしまいました」
「わざとだろう、朱里!」
乗馬用の鞭が朱里の頬に飛んだ。血が流れる。
ネイサンは血を見ることを好んだ。ウサギは元より、小鳥、ネコ、犬に至るまで、まるで虫のそれのようにいたぶっては殺すのだ。
ロレーヌ子爵は頭を悩ませた。遠い全寮制のミッション系寄宿学校にネイサンを送る。朱里を監視兼世話係として付けた。朱里は最初の頃こそただの世話係だったが、講師達からその優秀さを買われ、特待生扱いで同校に進学することになる。
「朱里、来いよ。遊ぼうぜ」
ネイサンの周りにはいつも暗い笑いを浮かべるご学友達が集った。「お前、また飛び級したんだってなぁ」
「召使い風情がエラソウに」
「優秀だね、朱里くぅん。頭の中が見てみたいよ」
「見てやろう、見てやろう」
「動くな、朱里」
朱里の黒髪がざくりとハサミで切り取られる。
翌日、懇意の講師が朱里の頭を見て、訝しんだ。
「床屋に行くのがメンドウで。自分で切って切りすぎました」
お構いにならず。髪などまたすぐに伸びます。
「……キーツの詩について、また君の意見を聞かせて貰えないかな、朱里君」
とっておきのお茶をだしてやろう。講師が言う。「君は早く大人になるべきだ。そしてその手っ取り早い手段を行うべき力を持っている」
講師が朱里の肩に手を置く。
「困ったものだ、子爵にも。彼は子どもを甘やかす術
「奥方様が早くにお亡くなりでしたから」
助けなどない、学ぶしかない。それしか術はないのだった。朱里は飛び級を繰りかえす。親しい友など出来なかった。朱里が先を急
とうとう卒業の年のその日。朱里は生まれ育ったロレーヌ子爵邸を後にした。
■■4
「刑事、今日は遅いお戻りでしたね」
帰って来たダグラスに居間で本を読んでいた朱里が言う。
「ああ、宝石の盗難事件が起こったんだ。また名家の家宝だよ」
シルキンクス夫人のピジョン・ルビーだ。夫人は息子に縋って「ご先祖様に申し訳が立たない」って泣き崩れててよ、供述をとるどころじゃなかった。その上、ルンペンの爺さん達を襲う愉快犯が最近目立っててよ。昨日も爺さんが一人病院に運ばれた。亡くなったよ。
「それは……大変でしたね」
ご褒美、と言っては何ですが、夕食に出した飲茶の残りがありますよ。
「ヤムチャ? なんだ、それ?」
「先日、紳士倶楽部で食べる機会に恵まれまして。調べて試作したものなのです。点心や果子
「旨そうだな」
「普段のお菓子作りよりかも、何倍も時間が掛かりました。是非召し上がって下さい」
ところで。と朱里が言う。
「暗記は進んでいらっしゃいますか?」
「あー、うー、まぁ」
「暗記のコツをお教えします。繰りかえすこと。地道に、コツコツと。刑事の職業と変わりません」
「ダラダラした作業はなぁ」ニガテだ、とダグラスが言う。
「ご褒美が付いてくるじゃないですか。確かにミシガン刑事の言うとおり貴方がキンバリーと同じ警部補に出世なされば、風向きが変わります」
「風はやっぱり吹くだろうがよ」
「では、こう言い直しましょう。風を遮る盾が出来る。ビビアン嬢のような弱い人達を守るための盾ですよ(作者注:幸福画廊16)」
朱里が飲茶を温め直しながら、台所から問いかける。
「刑事、宝石盗難事件はいつ頃から始まりましたっけ?」
「……ああ、一年前くらいからか、そういやぁ」
キンバリーが躍起になって追っているが、一向雲を掴むような様子らしい。
「左様で」
出された飲茶にダグラスが飛びつく。「旨いなぁ、旨いなぁ」
■
「ワタクシの美しい朱色・ヴァーミリオン。つれないのね。幾日待ってもワタクシのもとに来てもくれず。とうとうワタクシの方から来てしまいました」
小鳥がお茶を出そうとして指しだした手が緊張で震える。紅茶器は取り皿とスプーンが小さくカチャカチャと鳴っている。
「ありがとう、お嬢さん」
ダチュラ夫人が受け皿ごとカップを受け取る。夫人の手には相変わらず黒いレェスの手袋がはめられていた。夫人がカップを受け取っていなかったら、紅茶は皿に溢れ出していただろう。
「ヴァーミリオン?」
白野が口を開いた。朱色の別名だね。そうか、朱里の愛称なんだね。
「そうよ、エンジェルのような坊や。貴方が朱里の、この【幸福画廊】のマスターかしら?」
「うん。僕の名前は白野って言う。朱里は僕の執事だよ」
そして、この子が小鳥ちゃん。「メイドなんだ」と紹介する。
ダチュラ夫人が白野をじっと見る。ついで小鳥も。朱里も。この館の様子も。ゆっくりと撫でるように見回して「でも、来て良かったわ」と言う。
「人になったのね、ヴァーミリオン」
「マダム……」
と朱里。
「なぜここへ?」
言ったでしょう。貴方に会いに。それに……と「クスリ」と微笑う。まんざら知らないお屋敷でもありませんもの。
「白野坊や、大きくなったわね」
「……? 貴女、僕を知っているの?」
「貴方のお父様とは昵懇
白野の瞳が大きく見開かれる。小鳥が抱えていたポットを取り落としそうになる。
貴方
ダチュラ夫人が微笑んだ。
「そしてね、こんなチンケな屋敷からヴァーミリオンを解き放ってあげるのもワタクシ」
こんな、絵ばかりの家でつまらなく朽ちていく事なんて許さないわ、ヴァーミリオン。ワタクシがもっと素晴らしい世界を貴方にあげる。ついていらっしゃい、ヴァーミリオン。
「折角のお誘いですが、マダム」
朱里が言う。
「私はここにおります。私は【幸福画廊】の執事ですから」
■
その夜には、セント伯爵が館を訪れていた。
「朱里、Q紳士倶楽部では巧く立ち回っておるようだの」
「素晴らしい本に巡り会え、またご紹介頂きましたルイス大佐やウエストエンド元医師とも馴染みにさせて頂いております」
「うんうん」
と、老人が頷く。Q紳士倶楽部はすっかり有名になってしまって、つまらぬ輩も入会したがってくるからのぅ。お前さんのような若手が入ってくるなら安心じゃて。
「ところで、ダグラスの勉強の方はどうなっておるね?」
「頑張っておられますが、残念ながら仕事が押しているようです。宝石盗難事件の件で」
「ああ、シルキンクス夫人のピジョン・ルビーまで奪われたとか。界隈では大変な騒ぎじゃて」
「美しい大粒の宝石ばかりを盗んでいく泥棒なんですってね?」
「シルキンクス夫人の肖像画を僕、描いたことがあるから知ってるよ。ピジョン・ルビーって、あの血のように真っ赤な夫人がつけていた大きなブローチでしょう?」
小鳥と白野が言う。
「ある日突然、賊の入った痕跡もなく、家宝とも言うべき宝石が盗み出されておるそうじゃ」
ふいに、白野がポンと手を叩く。
「ダグラス刑事がその犯人を捕まえちゃえば、きっと昇級試験より早く昇進だね」
「そうですね、白野様。あ、でも、キンバリー警部補が邪魔してきそう」
小鳥が言う。皆が、不安そうな顔をする。
「そう言えば、ダチュラ夫人がQ紳士倶楽部に戻られたそうじゃの」
「ダチュラ夫人!」
小鳥が声を上げる。わたし、あんな綺麗な人見たことないです。そこに居るだけで周りを威圧するような美人っているものなんですねぇ。女優のナタリー・サンクレア(作者注:幸福画廊4、8)よりもずっとずっとすっごい美女。
「なんじゃ。小鳥ちゃん、ダチュラ夫人に会
「ダチュラ夫人は朱里に会いにこの館に来たんだよ」
「なんじゃと、朱里に?」
ヴァーミリオンなんてさ。笑わせる。
「白野様?」
あの飲茶もダチュラ夫人のお薦めだから作ったんだってね?
「僕、二度と飲茶なんて食べないから」
「白野様……」
「朱里はナタリー・サンクレアといい、あの夫人といい、趣味が悪いよ。アッカンベー、だ!」
白野が二階に駆け上がっていく。一同は呆然と見送った。
■
「朱里君、ちょっと話を聞いてくれないか」
「これはルイス大佐にセント伯爵。お揃いでどういうご用件です?」
Q紳士倶楽部の書庫に居た朱里が呼ばれて立ち上がる。
「ウエストエンド元医師と最近話をしたかね?」
「ドクターと? そう言えばご無沙汰しておりますが……」
すみません。書庫にばかり篭もっておりましたので。朱里が詫びる。
「いや、君がどうこうと言うことではないんだが」
二人が顔を見合わせた。まぁ、一緒にドクターに話しかけてみて、話はとにかくそれからだ。
「ドクター・ウエストエンド?」
「ああ、その声は朱里君だね。あと足音が二人。誰だったかな、この足音は……?」
「セントとルイス大佐じゃよ」
「おお、これは伯爵、大佐。お元気にやっておられますか?」
「まぁ、ぼつぼつじゃて」
セント老人が言いながら、ウエストエンド元医師の机の前に置かれているいつもの画集に触れる。
「今日は絵の話を聞かせて貰おうと思っての。是非、ターナーについて心ゆくまで語っておくれ」
そう言われて、ウエストエンド元医師が相好を崩した。
■
「分かったかね、朱里?」
「はい」
迎えの車に乗せられてウエストエンド元医師は帰って行った。セント伯爵とルイス大佐と朱里はビリヤード台の前に居る。そこが一番、人の目が少なかったからである。朱里がキューボールを突く。押されたカラーボールが力学の法則に従って動く。ポケットにカラーボールの一つが落ちる。
「認知症、かの?」
セント老人が言う。ウエストエンド元医師のこれまでのターナーの絵画指摘は完璧であった。見えぬ目で画集をめくる元医師は「これが海の見える絵、光の加減が格別だろう」や「こちらはターナーがイタリアへスケッチ旅行に出た時の絵」など、完璧に覚えて説明してくれていたものだ。それが、今日は……。
「ターナーは画面の色調を透明度の明るいものにする工夫に没頭した。そして書かれたのがこの絵だ。この絵は……はて、なんの絵だったか?」
「これはブルー・リージ。ブルーの……なにが描かれている?」
ターナー最晩年の作品、『ブルー・リージ』。ターナーの水彩画最高傑作ともいわれている作品であった。
これまでのウエストエンド元医師は若い頃から耽溺し、愛していた絵を見えぬ目蓋に鮮明に浮かべていた。それを生きるよすがとしていた。元医師の青ざめた顔が目に浮かぶ。
「私は、私は……。ああ、ターナー!」
あの絶望に満ちた顔。
クッションにキューで突かれたボールが当たる。ゴトゴトゴトンと稲妻の軌跡のように動いたカラーボールの一つがまた落ちる。
「それでの、朱里、わしらは二人で相談したんじゃが」
セント老人がキューにチョークを塗りながら言う。
「【幸福画廊】の奇跡をな、見せて欲しいと思うのじゃ。あの年老いた同胞のために」
「画廊の?」
朱里が聞き返した。次をショットミスする。セント老人の番だった。
■■5
「ヤだ」
と白野が言った。
「白野様?」
と朱里が問う。
「どうしてです?」
「Q紳士倶楽部が僕キライだから」
「白野様、お話し致しましたでしょう。ウエストエンド元医師には白野様のお力が必要です」
「どうして黙っていたのさ、あのダチュラ夫人って人を介してお前が館
あんな女
「分かっておりますよ」
「もう、Q紳士倶楽部なんて行っちゃダメだよ。朱里はあの人に捕まっちゃう」
ダチュラ夫人はその名のままに妖華であった。可憐とも優美とも言われる美しい花に似合わず、毒性が高く、幻覚を見せると言われているダチュラ。その花言葉の如く「夢の中」で「あなたを酔わせる」かのような射干玉
朱里がほぅーっと吐息を漏らす。
「……少し、遠くまで歩きましょうか?」
生憎の雨ですが、雨はお好きでしたでしょう?
白野が朱里を見上げる。しばらくお互いに黙っている。やがて、白野がこくりと頷いた。
■
幹線道路に近い、橋げたの傍である。辺りは公園のように整備され、木や花や所々にベンチも置いてあったが、今は雨の所為か、誰も居ない。朱里と白野は二人して、昔のように傘を差して立っている。
「白野様、ご覧なさい。あれが『他人の群れ』です」
橋を続々と渡っていく多くの人。その人波が間近に見える。早足の人、杖をついている人、傘を差していない人、男、女、子ども、老人。黙々と歩く人影は、皆、前を見て歩んでいる。
「ずっと、私はあの全てが他人の群れだと思っていました」
中には手を伸ばそうとしてくれた影もいた。その全てに背を向けて、ただ『他人の群れ』だと思うことで生きてきた。生きて来られた。自分とは違う第三者の群れなのだと。初めから属する場所が違うのだと。私はこの世にただ一人、アウトサイダーで部外者だと。
でも、白野様に出会いました。小鳥さんやダグラス刑事、セント伯爵とも出会いました。私達は元は他人でしたが、今は決してそうではない。
「あれは他人の群れじゃない。明日の友の群れなんです」
私はそれを知らなかった。誰も教えてくれなかった。白野様が私に教えて下さったんですよ。
白野が驚いた顔をする。蒼い瞳がまばたきする。
「僕?」
「そうです。【幸福画廊】の絵を介して私達は多くの人と出会った。その人の人生の一瞬を見た。過ぎ去っていったあの方達も、決して他人ではないのです」
皆が愛しい人達なんです。
「白野様、【幸福画廊】に助けを求めてきた人に、絵を描いてやっては頂けませんか?」
橋を続々と渡っていく多くの人。その人波が間近に見える。早足の人、杖をついている人、傘を差していない人、男、女、子ども、老人。色取り取りの傘が見える。色取り取りの人達が、今、何かを考えて橋を渡っていく。愛する人のこと、仕事のこと、悩みや怒り。
人の感情は「喜怒哀楽」というたった四文字で完結できるものじゃない。でも、その全てが不可欠で、それでこそ、人の生きる道を人生という。
■
「……分かった」
ゴメン。描くよ、僕。
僕が選んだ、僕の仕事だのにね。ゴメンね、ワガママ言っちゃった。
「我が儘は誰か偉い人、一人だけの持ち物ではありません。誰しもが持っていていいのです。貴方様も、そして私も」
「朱里のワガママって僕、聞いたことないなぁ」
白野がこくんと首を傾げる。
「私の我が儘はダチュラ夫人に会うことですよ」
ムムーン。白野が渋面を作る。
「あの女の人は毒華だよ。朱里、毒にあてられて捕まっちゃうんだから」
「そんな事はありません。私は……もう昔の私とは違いますからね」
それに、多少の毒への耐性もついています。
「耐性?」
「ええ。伊達に【幸福画廊】に長く暮らしてはおりませんからね」
「えー!」と白野が言う。
もう、朱里ってばひどいなぁ。二人は橋の方へ走り出す。走る二人の影が沢山の影に混じっていく。
■■6
「ダチュラ夫人、ああ、愛しい人」
その細腰に縋り付くようにしているのはネイサン・ロレーヌだ。
「”シャイン”が欲しいの、アナタ」
「分かっています。シャインは貴女にこそふさわしい。必ず、必ず」
フッフッフ。夫人が微笑む。今日はQ紳士倶楽部へ行ってみようかしら。ワタクシのヴァーミリオンは来ているかしら?
ネイサンがふと顔を上げる。
「なにを考えていらっしゃる?」
「……」
「あの下賤な男のことですか?」
「……ワタクシは宝石が好き」
夫人が言う。
「アナタは汚らわしい名で呼ぶけれど、あれも宝石なのよ。あんなに美しく光り輝くんですもの。人はねぇ皆宝石なの。光の強さは違えども、ね」
「宝石?」
ネイサンが鼻で嗤う。あれは虫けらですよ、ダチュラ夫人。
あいつが、我がロレーヌ家を出てから何をしていたと思います? いかがわしい娼婦風情に媚びへつらって、それで生きていたんですよ。働きもせず、ただ女達の中を点々と漂って囲われていた。
「時折は酒場の用心棒のようなこともやっていたようですが、あいつが宝石? 石ころにも劣る」
「それはアナタが彼にきちんとした紹介状の手配やまとまったお金を渡すことを、父君に反対した所為でしょう?」
夫人が微笑む。
あの子に他に生きる術があったかしら? 寄宿学校の先生達の紹介状も、みんなアナタが破り捨ててしまったのでしょう?」
「そんなこと! 一体誰に聞いたんです?」
「まぁ、ホホホ……。訊かなくても分かりますよ。巡り巡って、あの子を最後に飼っていたのはワタクシですもの」
「!」
ワタクシの見つけた宝物。ワタクシの美しい朱色の宝石・ヴァーミリオン。でも、まだあの子は不完全だった。まるでお人形のように生きる気力を失っていた。アレではダメ。ワタクシの大切な宝石にはなれない。……だから、一時
ネイサンがきつく唇を噛む。
「アイツは貴女のなんなんだ!?」
「そんなに妬かずとも、アナタも宝石を持っているじゃない、ネイサン」
アナタには”シャイン”の輝きがあるわ。それもワタクシにはとても大切。そっと手袋をつけた手でネイサンの頬を撫であげる。
「さぁ、行きましょう、ネイサン。紳士倶楽部へ。屹度
あの子は反抗期なのよ。執事風情が子爵令息であるアナタに逆らったり、ワタクシに会いには来なかったり、ワタクシを拒絶したり。少しおいたが過ぎるようね。お仕置きが必要。
ダチュラ夫人が妖艶に笑った。
■
ネイサンを従えるようにして、ダチュラ夫人が倶楽部に入る。丁度ドクター・ウエストエンドが居た。当然彼の盲導犬も。
「どけよ、爺さん」
ネイサンが老人の肩を押す。目の不自由な老人は足を揺るがせ転倒する。犬がウゥーと呻ると通り過ぎようとした夫人のドレスの裾を噛んだ。だが、訓練された犬のためか、すぐに離す。
犬の涎がダチュラ夫人のドレスの裾に付いた。それに気付いたネイサンが声を荒げる。
「このバカ犬が!」
キャィィン!
犬をネイサンが蹴り上げる。転がった犬のわき腹を執拗に蹴る。
「な、なにをする。やめろ! ジョンナー!」
ウエストエンド元医師が、見えぬ目でおろおろと止めようとする。
「ダチュラ夫人のドレスを汚すようなバカ犬なんて死ねばいいのさ、アンタみたいなボケタ老いぼれもなぁ!」
「おやめなさい、ネイサン。……おやめ」 ダチュラ夫人が眉を顰める。
「やめなさい!」
朗々とした声が響いた。ネイサンの繰り出した足が止まる。朱里以下、セント伯爵、ルイス大佐、他のQ紳士倶楽部のメンバーが立っていた。
朱里は歩み寄ると、ウエストエンド元医師の手を取る。セント老人がジョンナーの様子を見「すぐに獣医師の手配を」と言う。
「ネイサン・ロレーヌ、貴方を当Q紳士倶楽部から追放します」
「な、なんだと。仮会員のお前になんかにそんな事を言われる筋合いはない!」
仮会員ではありません。朱里が言う。
「四名と、もうお一人ダチュラ夫人。五人の承認をもって、私は当倶楽部の正規メンバーなんです。規約に従って貴方を永久追放処分とします。ご賛同の方、拍手を」
パチパチパチ。
拍手が上がった。喫煙室やビリヤード台の傍にいた紳士淑女も集まってくる。拍手の音が大きくなる。
「クッ!」
「警備員!」
セント老人が呼んだ。こいつをさっさとつまみ出せ! 嫌、それだけじゃあ済まされんなぁ。
「朱里や、こういう飼い犬への暴力は刑法でどういう扱いになる?」
「お任せ下さい。丁度ダグラス刑事の教科書で覚え込んだばかりです」
朱里が頼もしい事を言う。
「残念ながら傷害罪は適用されませんが、犬は持ち主のもの。器物損壊罪に当たります。立派な犯罪です」
「傷害罪もだろう、目の見えぬウエストエンドを突き飛ばし、転倒させた。わし達全員が証人だ」
ネイサン・ロレーヌが警備員二人に挟まれ、連れて行かれる。パトカーの音が響いてくる。ぐったりしたジョンナーをルイス大佐達が倶楽部の手配したタクシーに入れ、一緒に乗り込む。転倒でも怪我はなかったドクター・ウエストエンドも一緒だ。
「犬を虐めるだなんて、酷い事をするものですわね。あのロレーヌという男は」
ダチュラ夫人が言った。
皆が白々とした目で夫人を見ていた。
■■7
「相変わらず、貴方ときたら本ばかりね。あら、それは?」
【幸福画廊】の一室。朱里の私室であった。ダチュラ夫人の目線の先に成人と同じほどの大きさのテディ・ベアが壁により掛かって立っている。淡い茶色の細かい巻きのかかった毛並みで、首には極太の水色リボンを着けている。足の裏には『Dear Butler』の刺繍と、ご丁寧にピンクのハートのマーク付きである。
「クリスマス・プレゼントでして」
「まぁ」
ダチュラ夫人が笑う。バトラーなんて名前より、ワタクシの呼ぶヴァーミリオンの方がずっとステキよ。
「ネイサンを警察から出しておあげなさい」
ダチュラ夫人が言う。
「出来ません。ネイサンはウエストエンド元医師の盲導犬、ジョンナーの腹を蹴ったのです。ジョンナーは内臓破裂で危うい状態です。先程も申しましたが、器物損壊罪に当たります」
「罰金を払えば出られるでしょう?」
「ネイサンは余罪の追及を受けるでしょう」
恐らくいろいろとボロが出ます。父親のロレーヌ子爵でも庇いきれないほどのボロが。幾人もの物もらいの爺さん達が若者数人に暴行・殺害された事件がありましたね。目撃者の証言はネイサン・ロレーヌに似ています。
ネイサン、彼はやり過ぎた。
「でも、ワタクシまだネイサンに用事があるのよ」
「それは”シャイン”の事ですか?」
ロレーヌ子爵家の宝・ゴールデンサファイヤ”シャイン”。朱里も昔見せて貰った事がある美しい宝石だ。
「マダム、今までに貴族の子息達を誘惑し、騙して手にした宝石を全てお返し下さい。私は貴女に対して逮捕などと言う無粋な事をさせたくはない」
貴女は警察を甘く見ている。警察は必ず真実を暴き出すでしょう。
「アレは遊びよ。貴族のお遊び」
だって、折角の美しい宝石達は全てワタクシを喜ばせるためにあるんじゃなくって?
「……貴女は毒そのもののような方だ」
「ワタクシの可愛いヴァーミリオン。昔、貴方を連れて何処へでも行ったわ。ジャングルへでも地下倶楽部へも夜会にもオペラの桟敷席にも。燕尾服に身を包ませた貴方はとても美しかった」
「上流社会の事、裏社会の事、いろいろご指導下さいましたね」
今の私があるのはマダムのお陰です。おそばから離れるよう言われた時、少しお恨みもしましたが、今となっては本当に良かったと思っています。
「もう一度言うわ。ワタクシと一緒に来なさい、ヴァーミリオン」
貴方に贅沢をあげる。貴方に悦楽を上げる。貴方に冒険をあげる。貴方に陶酔をあげる。
一緒に行き、生きて、この世の全てを楽しみましょう!
「嫌ですよ」
「どうして!?」
「貴女が醜悪
その黒髪は今月何度お染めになりました? 年に何度、肌の張りを戻すために美容整形に行かれるのですか?
パシッ! と高い音がした。わなわなと夫人の黒いレェスの手袋の中の手が震えている。朱里は殴られた赤い頬に手をやる事もなく、ダチュラ夫人を横目に見る。
■
コンコン、と扉がノックされる音がした。
「あのー、朱里さん、お茶……キャァァァ!」
小鳥が金切り声を上げる。朱里の首元に怜悧なナイフを突きつけているダチュラ夫人の姿があった。
「ヴァーミリオン、お前はワタクシと来るのよ」
小鳥の悲鳴を聞きつけて、白野とちょうど帰宅したところだったダグラス刑事が駆けつけてくる。ダグラスが小鳥を押しのけて室内に入り、場を察するとすぐさま拳銃を抜く。
「やめろ、ナイフを卸せ、警察だ!」
「撃たないで下さい、刑事!」
その時、特大のテディ・ベアがぐらりと動き、朱里とダチュラ夫人の所に倒れかかる。
「ツッ」
夫人がナイフを取り落とす。それを逃さず朱里の長い足がベットの下へとナイフを蹴り込んだ。
「手を上げろ! ……誰だか知らんが。執事の情婦か?」
「マダム、もう諦めて下さい。マダ……」
スローモーションのように影が動いてガラスが割れた。ダチュラ夫人は窓の外へと真っ逆さまに落ちていく。
「マダム!」
朱里が走り出す。階下に目がけて駆けていく。
ああ、あの時もそうだった。白野様の父君の時も……。
ガラスの破片にまみれて、黒髪の女が横たわっている。
「ゴフッ」と口唇から血が溢れる。口紅の色と同じ赤だった。
「……マダム」
ダチュラ夫人が薄く微笑む。朱里の赤くなったままの頬にそっとその手を当てる。
「……貴方こそワタクシの最高、の……美しい宝石だったわ。……ヴァー、ミリオン」
「マダム……」
「最期に、ワタクシの名、呼んで……」
「ユーディット!」
館の他の三人が集まってくる。ダグラスは小鳥の肩を抱いている。ファンファンファンと、サイレンの音が聞こえてくる。朱里は黙したまま、俯いている。
■■エピローグ
「じゃあドクター、絵を『見て』ね」
白野が言う。一枚の油彩画がウエストエンド元医師の座るテーブルの前に置かれた。ドクターが戸惑った顔をする。
「触って『見て』」
ウエストエンドの手がおそるおそる伸ばされる。絵に触れて、ハッとしたように息を詰める。青い山の稜線を手でなぞる。
「これは、この絵はターナーの『ブルー・リージ』か」
本来、水彩画であるはずの絵を、目の見えぬ愛好家のために絵の具をぼってりとした厚みで描
「あと、二枚あるんじゃぞい。『戦艦テメレール号』と『アップナー城』じゃ」
「おお、おお……」
ウエストエンドの手が絵の上をなぞる。
「アップナー城の犬がいる!」
クゥーン、と傍らの犬が鳴いた。ジョンナーだ。元気になってまた飼い主の傍に控えている。
「もし、他の絵もお望みでしたなら、白野様は描くと仰っています」
「お願いしたい。朝焼けの絵も、海の絵も。……ああ、なんて素晴らしいんだ」
セント伯爵、ルイス大佐ありがとう。ありがとう。
ウエストエンド元医師が涙をこぼす。
「朱里君、君にもありがとう」
「お礼はどうぞ我が主人に。私どもは【幸福画廊】でございますから」
何度もお礼を言い、三人で喜び合うQ紳士倶楽部の先輩達と白野に、朱里は黙礼すると部屋を出た。
■
「うぉーい、執事ぃ」
Q紳士倶楽部の戸口でダグラス刑事が呼ぶ。
「供述調書やらなんやら、お疲れさんだったな」
「刑事こそ、晴れて警部補にご出世ですね。おめでとうございます」
あ、刑事と呼んではダメでしたね。これからは警部補とお呼びしなくては。
「あー、イイ、イイ」 ダグラスが嫌そうな顔をする。「呼称は刑事のままでイイ」
それに朱里がゆっくりと笑む。
「今夜は早く戻って下さい。小鳥さんが刑事の昇進祝いパーティを開くそうですよ」
この時間にお前がここにいるって事は、またもや小鳥のメシなのか? と、ダグラスが空恐ろしそうに言う。
「てか、俺は未だに意味がよく飲み込めないんだが。連続宝石盗難事件犯と、ルンペン爺さん達を襲ってた犯人が、なんで芋づる式にこのQ紳士倶楽部から出てきたんだ?」
ダグラスが首を捻る。朱里がこの倶楽部で逮捕されたネイサン・ロレーヌをオヤジ狩り事件の主犯だといい、館で投身自殺した謎の美女を宝石窃盗犯だと告げた。ダチュラ夫人、本名ユーディット・クリムトの館からは宝石以外にも多くの盗品が押収された。
全くさっぱり分からねぇ、と何度も首を捻る刑事に、
「まぁまぁ。刑事も宝石窃盗犯の犯人にはおおよその目星を付けておられましたでしょう?」
「まぁな、全部が内部からの犯行だって察しだけは……。でも、まだそれだけだったんだぞ。……あの女は一体お前の何だったんだ?」
「刑事。私は今回、白野様に【幸福画廊】の絵を描いて頂くために、一つ嘘を吐
「ん?」
朱里が前を見つめる。往来を歩く人々が行き交う。
「私はあれを他人の群れじゃない。明日の友の群れなんだと、そう白野様にお話ししました」
【幸福画廊】の絵を介して私達は多くの人と出会った。その人の人生の一瞬を見た。過ぎ去っていったあの方達も、決して他人ではないのです。皆が愛しい人達なんです、と。
「ですが、どうしても相容れぬ人はやはりいます。どんなに惹かれようとも、どんなに魅惑的だろうとも、一緒に歩いてはいけない人が。……あの女性
ただ離れればそれで済むと思っていたのに、遠い所へ去って逝かれました。白野様に言ったのは方便です。きっと、共に歩めぬ人は思う以上に大勢いる。
朱里が片手を上げる。すっと伸ばすと、こちらになど気づきもせずに行き交う人々を指差した。
「ほら、刑事、ご覧なさい。他人の群れが歩いて行きます」
■■後書き
前作からこんだ5日しか経っていません。14年ぶりに画廊メンツと再会……と思っていたら、この快挙。誰か褒めてー、私を褒めてー。まぁ14年も前の作品なんて誰も覚えちゃいないと思うんですけども、ずっと、どうしても、この話だけは何年経っても私が死ぬ前に書かなければ、と思っていたので書きました。朱里の過去のお話です。全伏線回収、私乙(多分)。やっと書けてほっとしてます。お読み頂いて本当にありがとうございました。
あ、尚、作中に登場する妖しき女性・ダチュラ夫人。これはグスタフ・クリムトの有名な絵画「ユーディット」を参考にしています。絵を載せておきますね。あと、ダチュラ(チョウセンアサガオ)の写真も。よろしければ、ご感想などお寄せください。
宇苅つい拝


ツイート よければTweetもしてやってね |