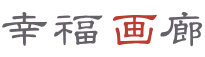
第12話
「 不審人物 」
■■プロローグ
「C国の古い民話や伝承についての文献ですね?」
「はい」
復唱された質問に、黒髪黒服長身の男が頷いてみせる。
朱里は市の図書施設を訪れていた。近隣ではかなり知られた図書館で、蔵書数には定評がある。
「お探しの本は……C-703の書架にございます」
そう言って、カウンターに座った司書の女の子が館内図を示す。
「カフェテリア横の階段から二階に上がられて、まっすぐ。突き当たりを右に進んで……こう、こう、こう……」
司書の指先が順路を辿る。該当書架は随分奥まった場所にあった。C国文献は冷遇されているらしい。朱里が館内図を頭に入れるべく、わずかに身を乗り出した。自然、カウンター内の女の子との距離が縮まる。男の肩口で結わえた黒髪がサラリと肩を流れ落ちた。その微かな音を耳にして。彼女の頬はみるみるうちに赤く染まる。
「どうも」
目の前の女性の火照った頬に気づいているのかいないのか、男は礼を言うと、教えられた階段に向かおうとする。カフェテリアのオレンジの看板が目印だ。
「あ、待って!」
司書が呼び止めた。振り返る男に、彼女はしどろもどろになる。思わず立ち上がってしまったこの衝動をなんと言い訳したものか。
「あ……、いえ、そのぉ。や、やっぱりご案内しましょうか?」
「いえ、それには及びません」
女の子からの申し出を断わると、朱里はそのままスタスタと立ち去って行ってしまう。彼の長身が見えなくなると、途端に同僚の若い女の子達がカウンターに飛んできた。
「ちょっと、ねぇねぇ、今の人!」
「すっごいハンサム!」
「背ぇ高ーい!」
うわずった忍び声、という、かなりに高度な発声法
■
階段を登る前。朱里はカフェテリアと図書館の仕切りになっているガラス壁に映り込んだ自分の姿をチラリと見た。トレードマークの黒のスーツの右半分を今一度確認する。泥のハネは目立たないが、まだ点々と残る湿った感触が鬱陶しい。
本来、徐行運転するべき図書館の敷地内を、結構なスピードで走り出ていく車があった。その車が昨日夜半に降った雨で出来た水溜まりの水を、思いっきり朱里に浴びせてくれたのである。
これからこの図書館で行なうべき調べ物の億劫さとも相まって、朱里の虫の居所は何時になく、すこぶるつきで悪いのだった。
■■1
C国文献のフロアは閑散としていた。閲覧席に座っているのは、禿頭
目的の書架にたどり着くと、朱里はそこに居並ぶ書物の背表紙を見渡した。場所的には冷遇されているが、冊数としてはかなりなものだ。有り難いような、ちっとも有り難くないような。
「さて、どの辺から手を付けたものですかね?」
口中小さく呟いて、試しに目の前の棚から一冊を抜き出す。索引を捲る。
朱里は彼の主人である白野に言われて、この図書館を訪れている。美術品コレクターであるセント伯爵の紅茶器に絡んだとある理由から、C国で吉鳥とされる伝説上の鳥・鳳凰について、その伝承内容を調べる必要が生じた為だ。もっと端的に述べるなら、「鳳凰がその足を枷
始めから確かに「在る」と分かっている調べ物ならともかく、「無い」可能性を含む調べ物はとにかくもって難しい。早々に「在る」ことが分かってくれれば無問題だが、それが見つからない場合。「無い」と見切りを付けるべき目安が、例えこの図書館に収蔵された全ての関連文献をしらみつぶしに調べたところで、果たして見つかるのかどうか……。
まぁ、それでも。
「白野様の厳命とあっては、致し方ありませんねぇ」
一応の目星を付けてみた数冊の本を手に、閲覧席に腰を下ろした朱里は、ため息混じりに小さくゴチる。
今の彼の台詞を白野が聞いていたとしたら、少年はきっと、
「僕、命令なんてしてないよ。お願いしただけ」 と、おっとり顔で言うのだろう。あの大きな蒼い瞳で朱里を見上げて。
確かに「お願い口調」ではあったが、あの蒼い瞳はクセモノなのだ。白野がまだ幼かった時分からこっち、無念ながらあの瞳に逆らえた覚えが朱里にはただの一度もナイ。主従関係にあるからとかの理屈ではなく、ほとんど条件反射である。それを当の少年主
「……どうして逆らえないんですかねぇ?」
我が身のことのクセに、朱里はまるで他人事のように、不思議そうに首を捻る。
実は、あの蒼い瞳からは、普通の人間には不可視の謎の怪光線でも出ているのではなかろうか? 仕える立場で言うのもナンだが、元から摩訶不思議な主なので。……かなりあり得る。
ちょっとコワイ、と朱里は思った。
調べ物をしていると、窓の外に一羽の鳩が飛んできた。この図書館の隣には公園がある。そこからやって来たのだろう。クックルー、クックルーと鳴く鳩を頬杖を付いてぼんやりと見る。気が付けば、二列前の席に座る老人も、首だけ巡らせて鳩を見ていた。目線があって、何となく互いに軽い会釈を交わす。鳩が空へと帰っていき、朱里は再び開いた本に目を落とす。
■
結局、閉館近くまで調べ物に没頭し、窓の外の暗さに気づいて、慌てて館に帰ってきた。朱里が居間の扉を開けると、ソファーに座って手にした冊子に何事か書き付けていた小鳥が顔を上げ、「お帰りなさい」を言ってくれる。彼女の膝の上に広げられたページには細かい升目で構成された複雑な模様が見て取れた。クロスワードパズルの雑誌らしい。
「随分遅かったのね」
「すみません。夕食は?」
「ごめんなさい。先に白野様と食べちゃった」
小鳥が気を利かせて夕食の支度をしてくれたようだ。それはとても有り難いが……果たして食べられるシロモノだったのか? 多少不安だったりする。
「朱里さんこそ、食事は?」
「まだです」
「じゃあ、すぐに用意するわね。今日は煮込みうどんを作ったの」
「……」
この温かい季節に煮込みうどん。いや、別に作って悪いという決まりはないが。
煮込みすぎて麺が伸びきってしまっても言い訳が立つからだな、と朱里は思う。多分、確実に当たっている。
「おまたせ」
待つこと10分。テーブルに着いた朱里の前にドンッと丼が置かれる。
「頂きます」
具は野菜に鶏肉と豊富だ。セロリの入ったうどんというのは初めてだが。先ずは汁から。ふむ、だしの味は悪くない。……いや、白野様の好みからすると多少塩辛いだろうか?
そんな、白野の舌を基準にした自分の考えに気づいて、朱里は心中大きく肩を竦める。つくづくと、白野至上主義の考え方が身に染みついているのだった。まぁ、改める気は皆無である。今更過ぎる、そう思う。
さて、それよりも問題は。
「小鳥さん」
「はい?」
「乾麺を茹でる時には、麺を熱湯に入れてからしばらくは鍋をかき混ぜ続けて下さい」
「へ?」
「そうでないと」
朱里が箸で麺をすくってみせる。数本の麺が互いに貼り付き合って、太い一本になっている。
「こんな風に、麺同士がくっついてしまうんです。一度くっついた麺は後から幾ら混ぜたところで、もう剥がれることはありません」
そうなると煮え具合にもムラが出来て、食感を損ねてしまいます。パスタ類全般に言える注意事項です、と講釈を垂れる。
「えぇー、そうなの!?」
小鳥が目を丸くした。
「シコシコした美味しい麺に茹で上がったと思ってたのにぃー」
そんな、そんな、と、両の手で自分の頬を押さえて、プルプルプルと首を振る。
「だって、白野様もね、『コレは三本繋がってる。あ、こっちのは五本だー』とか仰って、楽しそうに食べて下さってたんだからぁ」
「……」
思わず知らず、ガックリと肩が落ちた。小鳥さんも小鳥さんなら、白野様も白野様だ。なんだか、どっと疲れてしまった。私はメイド教育も主の教育も、何処かで間違えてしまったのだろうか? 箸ですくい上げたセロリの切れ端を、ただ黙々と噛みしめる。
■
「……ところで、その白野様は?」
茹で直してきます、と叫ぶ小鳥に、次回から気を付けて下さればそれで結構ですから、と返して。朱里は主の所在を訊ねる。
「ああ、それがね」
向かい合った席に腰を下ろした小鳥が言った。
「白野様ったら、今日は一日中あくびばっかりなさってて。朱里さんが帰る少し前に、お休みになってしまったの」
朱里は腕時計を確認する。まだ9時前だ。
「……そう言えば、今朝は寝起きが悪いご様子でしたっけね」
朝食時間になっても階下に降りてこないので、朱里が様子見に行ったのだった。画廊に絵の依頼が入っている時などは、明け方までアトリエに篭もっていたり、生活が不規則になる白野だが、普段はかなり規則正しい。ここは朱里の教育の賜物である。
朝、カーテンを開け広げ、まだベットの中だった白野に向かって声を掛けると、
「……あ、やっと朱里が起こしに来てくれた。待ってたんだよ。……助かった」
などと、まだ夢うつつ、といった風情で、謎な台詞を呟いていた。
「あのね。白野様、昨夜
「おや、そうだったんですか?」
それで「助かった」だったのか、ああ成る程、と納得する。
「白野様、今夜はどんな夢をご覧になっているのかしらね?」
食べ終えた朱里の丼を片づけながら小鳥が言う。二人揃って、何となく階上を見上げてしまう。
この館の主の見る夢は、いつも楽しい夢だと良い。
■■2
朱里が図書館に通い始めて数日が経つ。今のところ、鳳凰が枷で繋がれた逸話というのは、一つも見つかってはいない。それどころか、本にある鳳凰の描写が伯爵邸で見た鳥の絵と、かなり食い違っていることに気づいてしまった。どうも根本に立ち返った方が良さそうだ。
そろそろオープン書架に置かれている本では埒が明かなくなってきていて、閉架書庫の文献を漁り始めた朱里である。目録を調べ、必要事項を書類に記入した上で、いちいち係員の手を介して書庫から本を取ってきて貰わなければならないので、効率は著しく悪くなる。
閉架書庫閲覧の申請書に必要事項を記入する時、職種の欄にちょっとふざけて「サービス業」と書いてみた。
その事に深い理由はない。ただ、自分の日常は「執事」というより、「便利屋」とか「何でも屋」に近いな、と思っただけだ。今朝も早朝から庭の草を刈り、最近吸引力が落ちてきたという掃除機を修理し、工具箱を出したついでに玄関口の電球も取り替えた。
そんなこんなで、普段よりかなり遅い時間になってしまった朝食の席では、先ず、白野が砂糖壺をひっくり返した。いかにも寝が足りない、という顔で、「ゴメンナサイ」と頭をカクンと縦に落として謝ってみせる。テーブルを片づけて朝食を再開すると、今度は小鳥が、どうしても解けないというクロスワードパズルの答えを、それはヒツコク訊いてくる。
「『C』で始まって『R,I,E』で終わる11文字の言葉よ。『17世紀から18世紀に流行した』ってなにー? なにー? なーにー?」
「『シノワズリ』です。『C,H,I,N,O,I,S,E,RIE』」
教わった綴りを升目の中に埋めていく小鳥の目が輝いた。
「ああ、ココには『N』が入るんだ。じゃあ、この縦のラインも分かっちゃったもーん、わ、た、し」
嬉しそうに鼻歌混じりで縦の答えも書き込んで。それからふと、首を捻った。
「……でも、『シノワズリ』ってナニかしら?」
「僕も知らないな。どういう意味?」
主とメイドが揃って、子犬のような目で訊いてくるのに、「二人で仲良く辞書を引いてみましょうね」 と、そう笑って言ってやった。
書き終えた申請書をカウンターに提出しつつ、朱里はそんな朝の会話を思いだして、ほくそ笑んだ。自分だけが辞書と首っ引きというのは割に合わない、と感じていたところだったので、ちょっと溜飲を下げた気分だ。そう言えば、『シノワズリ……C国趣味』とは、それなりにタイムリーで何だか意味深な言葉である。
■
「この本でよろしかったですか?」
司書が本を手に戻ってきた。申請したタイトルであることを確認して受け取る。
「どうも」
「お待たせしてしまってすみません」
そう謝ってくる女の子の口紅の色は、朱里が図書館通いを始める前と比べると、確実に濃くなっている。それに当の男が気づいてくれてなさそうなのが、彼女には不満であり、同時にその素っ気なさがまたステキだとも思うのだった。女心は複雑である。
「いえ」
司書の浮かべる最上級の笑顔などには目もくれず、朱里はさっさとカウンターを離れていく。
あああああ〜、行ってしまう〜。
「あ、あの……」
振り返った長身に、司書が言う。
「あの、閉架書庫の本は全て持ち出し禁止となっておりますので、閲覧は館内でのみお願いしますね」
「はい」
更に数歩歩いたところで、もう一度呼び止められた。
「あ、あのぉ……」
「……?」
「あの、その、し、調べ物、頑張って下さい!」
「……どうも」
閲覧室へ向かいつつ、朱里はこめかみを指で揉んだ。
■
「ビッグニュース!」
先程、カウンターで朱里の応対をしていた女の子が、給湯室に駆け込んで来た。他の司書仲間の女の子達はインスタントコーヒーを飲んでいる。
「なによ? お局様の電撃結婚の話なら、みんなとっくに知ってるからね」
「違うわよ。あの謎のハンサムの名前がとうとう分かったの!」
「ジャーン!」と一枚の書類を目の前でかざす。
「おおぉ〜」
他の子達が寄ってきた。
「閉架書庫閲覧の申請書ね?」
「でかしたっっ!」
ナニが「でかした」なのか意味不明だが、女の子達の視線は紙切れ一枚に集中する。
「……『朱里』。朱里サマかぁ〜」
「ステキな名前」
「お仕事はナニしてる人?」
「えーっとねぇ、『サービス業』だって」
個人情報の漏洩防止などというお題目は、彼女たちの大いなる好奇心の前には全くもって無力である。
「んー、サービス業って言っても、幅が広いわよねぇ」
「そうよねー」
「あの髪型からして、普通の会社員じゃあないと思うの」
「C国の文献を調べてるのよ。どこかの大学の研究者でしょう?」
「それは『サービス業』じゃナイわよぅ」
謎は深まるばかりだが、その謎多きところが更に乙女の夢を誘うのだ。女の子達は推理合戦に熱中する。とうとうお局様がしびれを切らせて怒鳴りつけに来るまで、彼女たちの激論は続いたのだった。
■
「おや、どうしましたね? 浮かぬ顔をして」
すっかり定位置になっているC国文献フロアに戻ると、これもそこを根城にしている老人が、朱里に向かって笑いかけた。朱里も老人も毎日この図書館に通っており、しかもフロアにはいつも二人きりなので、いつの間にか言葉を交わすようになっていたのだ。
老人はフーパーと名乗った。小さな会社の事務員だったが、今は引退して年金暮らしであるらしい。妻には早くに先立たれ、子どもも居ない。そんな寂しい暮らしの中での唯一の楽しみが、この図書館でC国についてのあれこれを研究することなのだそうだ。
「昔、妻にせがまれて行った新婚旅行。その時のC国のエキゾチックな美しさが未だに忘れられんのです」
フーパー老人はそんな事を言って、毛のない頭をかきかき照れ笑いする。その指には今も銀色の結婚指輪が嵌っていた。仲の良い夫婦であったに違いない。
「いえ、閉架書庫の本を借りてみたのですが、手続きが手間だなと思いまして」
「おやおや、あんたさんくらいイイ男なら、司書の女の子達が先を争って本を出してきてくれるでしょうに」
知ってますぞ。彼女達がしょっちゅうあんたさんの噂話をしてるのを。羨ましいですなぁ、お若いというのは。
老人がカラカラと笑うのを、朱里は黙って聞いている。
「いや、ウチの下宿人二人も、あんたさんくらいモテると良いんですが。どっちも気の良い若者ですからね。良い嫁さんを世話してやりたいもんですよ」
「トンプソン氏とマードック氏でしたね?」
朱里は、毎日老人を迎えに来る男達の顔を思い出す。一人は痩せて鋭い目をした短髪の男だ。そしてもう一人は小柄で、始終ガムをクチャクチャ噛んでいる目線の定まらない男。二人とも三十代半ばから四十という年齢だが、フーパー老人から見れば、朱里と同じく、充分若者なのだろう。
「ええ、今時の若いのにしては、本当に出来た奴らですよ。わたしがまたこの図書館に通えるようになったのも、彼らのお陰ですからね」
老人は自分の右足をポンポンと叩く。膝を痛めてから、もう長く図書館通いを諦めていた老人を、下宿人の二人が車で送り迎えしてくれるようになり、老人は再び趣味の時間を持つことが出来るようになったのだ。もう、フーパー氏から何度も聞かされた自慢話である。
朱里は、老人の隣りの席に腰を下ろした。折角借りてきた本は、机の上で閉じられたままだ。
「本当に人柄の良い下宿人達なんですね。よろしければ、もっとお話しを聞かせて下さい」
手の平を軽く組んで、そう促す。
「ええ、いいですとも。本当にわたしら夫婦に息子が居たらあんな風かと思いますよ。まあ、唯一の難点が、二人揃ってカメラ狂いってことでしょうかな? ウチの地下室を暗室代わりに始終篭もっておりますよ。それにしたって……」
老人が楽しげに語るのを、朱里はじっと聞いている。時折相づちを返しながら。
■
やがて、夕刻になり、フーパー老人の自慢の下宿人が彼を迎えにやってきた。
「フーパーさん、お迎えですよ。今日はどんな本に出会えましたか?」
クチャクチャとガムを噛みながら、朗らかな笑顔で老人に向かって問いかける。
「おお、トンプソン。今日は桃源郷についての本を読んだよ。いつも送り迎え、すまないなぁ」
「何を仰るんです。同じ屋根の下に住まわせて貰ってるんですから、これくらい当然のことですよ」
杖をつく老人の肩を労るようにして、フロアを出て行く。
「それじゃあ、朱里さん。また明日」
「はい。またC国の旅の話でもお聞かせ下さい、フーパーさん」
朱里も笑って挨拶する。トンプソンがひょこんと頭を屈めて朱里に黙礼してみせた。
しばらくして。男が車でフーパーを連れ帰るのを、朱里は図書館の窓から見下ろしている。門を出て行った車を見送って、席に戻った。
ジャリ、とつい今し方まで床には存在しなかった感触が靴底に触れる。土だった。
■■3
今日も図書館の閉館ギリギリまで調べ物をした朱里が館に戻ると、待ちかねたように小鳥が玄関まで迎えに来た。ナニやら深刻めいた表情
「ねぇ、白野様がおかしいの」
「おかしいって、何がです?」
長時間同じ姿勢で本を読んでいた所為で、凝ってしまった首をコキコキ回しながら居間へ行く。男の服を離そうとしない小鳥は、必然的に後ろからへばりつくように付いてくる。居間の扉を開けても、そこに少年の姿はなかった。白野は今夜も早くから寝てしまっているらしい。
「四六時中、眠たそうになさってるし、それにヘビの絵ばっかり描いていらっしゃるのよ」
「ヘビ?」
「ヘビ!」
しかめっ面で「もう、白野様のスケッチブックったら、ヘビだらけ」と訴える。まあ、女の子でヘビが大好きだという話はあまり聞いたことがないので、宜
ソファーに腰を下ろした朱里が、「それで?」と促すのに、小鳥が声をひそめてこう言った。
「それでね、わたし思うんだけど。もしかして、白野様、ヘビに取り憑かれちゃったんじゃあないかしら?」
一瞬、思考が停止した。ただでさえ、気の張る作業を終えて帰ってくれば、小鳥は今、何と言った?
「……は?」
「だって、ヘビって冬眠するでしょう? 白野様ホントに眠たそうで」
「小鳥さん、冬に寝るから『冬眠』というんです。今の季節を考えなさい」
確かに、最近の白野様は始終眠そうにしていらっしゃるようですが。ヘビの絵もお描きかもしれませんが。だからって、どこをどう弄くったらそういう突飛な発想が湧くんです?
深く息を吐きつつ、そう諭す。疲れ目の所為か、軽く痛むこめかみを指で揉む。
「あのね、庭の草刈りをしたじゃない?」
「はい」
「その時、気づかずにヘビの巣を壊してしまったとか、ヘビのしっぽを踏んづけたとか、何かヘビを怒らせるような真似をして祟られたんじゃないかしら?」
「私と小鳥さんで作業したんですよ。どうして白野様が祟られるんです?」
「それは……やっぱり、この家のご主人様だし……」
「……」
ダメだ。さっぱり解らない。小鳥の思考は朱里の理解の範疇を遠く超える。ついていけない。というか、ついていきたくない。決して。
「確かに、この屋敷の庭は広いですし、手入れも充分に行き届いているとは言えませんから、ヘビの2、3匹は居そうですがね」
白野様は普段から茫洋となさった方ですし、気まぐれに何かの絵に執着なさることも、これまで何度もあったでしょう。
「大丈夫ですよ。考えすぎです、小鳥さん」
■
これでこの話はお終い、という風に立ち上がり、台所に行くと、朱里は冷蔵庫から缶ビールを取り出す。三日と開けずに泊まりに来るダグラス刑事の常備品だ。朱里は酒好きの割にビールは滅多に飲まないが、今夜はひどく飲みたい気分になってしまった。
「そういえば、お夕飯は?」と後ろにくっついてきた小鳥が訊くのに、「途中の店で済ませました」と返しつつ、また居間に戻る。やはり小鳥はついてくる。
「でもね、じゃあ、どうしてヘビの絵なんか……」
ネチコク話を蒸し返す小鳥に、内心深々とため息をつく。プルトップを開けて一口啜ると、ホップの苦みが喉に染み渡るのと一緒に、小さな悪戯心が沸いてきた。
いかにも深刻そうな顔を作って言ってみる。
「……そうですね。白野様は財テクに目覚められたのかもしれません。ヘビはC国では金運の象徴なんですよ」
などと、最近の調べ事の成果の一端を披露する。
「もしも、スケッチブックのヘビに黄色い絵の具が塗られるようでしたら、確定ですね。風水もやっておられるのでしょう」
したり顔でそう頷く。小鳥が半信半疑の顔をした。更にたたみ掛けてみる。
「白野様が財テクに目覚めたのなら、私どもも考えませんと。給金を減らさせる可能性が出てきます」
「えっ!?」
そんな。この前、花柄のワンピースと同じ色のパンプスをカードで買ったばっかりなのに。
サッと青ざめた小鳥に、朱里が堪らず吹き出してしまう。
相変わらず、素直なお嬢さんである。からかい甲斐があり過ぎる。
「朱里さん、わたしはマジメに白野様のこと心配してるのよ!」
騙された、と気づいた小鳥が顔を真っ赤にして怒った。
■
「白野様が奇矯なのはいつものことです。彼の舌が細く伸びて二つに割れるなり、手足に鱗が生えるなりしたら、また報告して下さい」
朱里はそう言い置いて、席を立った。飲みかけの缶ビールを手にしたまま、階段に向かう。
丁度、そこにダグラスが帰ってきた。既に屋敷の合い鍵まで持っている彼である。ほぼ同居、と言えたが、アパートの荷物を移す手間がメンドウだという理由から、未だに正式なこの屋敷の住人にはなっていない。刑事という職業柄、二つの家を行き来する方が彼には都合が良いのかもしれない。
「今帰ったぞー、執事」
「おや、刑事。今夜はこちらにご帰還ですか?」
おう、洗濯物が溜まったんでな、と大きな紙袋をひょいと上げてみせる。彼のアパートの洗濯機は壊れてからもう数ヶ月、一向に修理される気配がない。
「……なんだ? なんか、小鳥があっちの方で喚いてないか?」
ダグラスが居間の方から聞こえてくる奇声に耳を澄ますのに、笑って答える。
「今、その洗濯物の山を渡したら、確実に頭の上でひっくり返されると思います。明日になさった方が良いですよ」
「小鳥のヒスは怖いからなぁー」
クワバラ、クワバラ……と呟きながら、ダグラスも朱里について階段を登る。コソコソとした忍び足だ。
「……ああ、刑事。一缶頂いてしまいました」
手にしたビールを思いだして、そう朱里が断わりを入れる。
「ん? お前がビールってのは珍しいな」
「まあ、たまには」
「フフーン、疲れた時にはビールに限るだろ? 喉に染みる旨さだろうが」
ダグラスがにんまりと笑う。そうですね、と相づちを打った。
「刑事」
二階につくと、朱里はダグラスを呼び止めた。右に曲がるダグラスと反対に朱里は左の方につま先を向けている。廊下の左の端には白野のアトリエと寝室がある。
「ああーん?」
大あくびをしながら、ダグラスが振り返る。
「明日、お暇な時でいいですから、図書館までご足労願えませんか?」
「あ?」
「どうぞ、よろしく」
そう言い残して、朱里は白野の部屋に消えていく。
■
コンコン、と軽くノックしてみたが、当然ながら返答はない。
朱里は白野の寝室のドアを音を立てぬよう、そっと開いた。少年の規則正しい寝息が聞こえる。扉は薄く開けたまま、室内に入る。
サイドテーブルのランプは点いたままだった。
ビールの缶を置いて、代わりにテーブルに置かれた彼のスケッチブックを取る。中を見ると、成る程。小鳥の報告通り、どのページも全てヘビの絵で埋められている。他に置かれているスケッチブックにもヘビの絵ばかりが描かれているのだとしたら。確かにちょっと尋常でない。
「……さて、今度は一体どんな気まぐれなのでしょうね?」
心中で呟く。その声が聞き取れた訳でもないのだろうが、白野がベッドの中で寝返りを打つ気配がした。「うぅん……」と小さく吐息を漏らす。それに続けて、巧く呂律の回らぬ声がほんのひと言寝言を言った。
「……くたびれた」
朱里の片眉が僅かに上がった。笑いを噛み殺すのに苦労する。一体、この年若き主はどんな夢を見ているのだろう?
「くたびれた」という言葉の割に、のほほんとしたその寝顔。
心配は無用だな、と思う。どちらかというと、気苦労の種が尽きないのは自分の方な気もする。小鳥は相変わらず必要以上に元気だし、鳥に関する調べ物にもまだまだ時間が掛かりそうだ。……というか、実は紅茶器の方の調べ物はすっかり後回しになっている。朱里はそれとは全く別の件に現在囚われていたりするのだった。
まあ、これは彼にとって、多分に『気晴らし』の意味も含んでいたが。
サイドテーブルのランプを消した。
自室に戻ったところで、ビールを白野の部屋に置き忘れてきたことに気がついた。
惜しい、と思いつつ、あきらめる。
■
朝、朱里はいつもより早い時刻に目を覚ました。階下に降りると、白野がソファーに座って絵を描いている。多分、ヘビの絵なのだろう。
「おはようございます。今日はまた、随分早起きされましたね」
「うん。何となく目が覚めた」
目が覚めた、と言いながら、ふわぁーと眠そうなあくびをする。
「ダグラス刑事がね、ちょっと前に出て行ったよ」
何か事件があったみたい。でも、午後からならそっちに行けるだろうって伝えてくれって頼まれた。
「そうですか」
早朝から事件とは、刑事家業も大変である。
お湯を沸かして紅茶を煎れる。「ちょっと早いですが、朝食になさいますか?」と訊ねると、首が横に振られた。
「要らない。……多分また寝ちゃうと思うし」
ヘビの絵が描き上がったのか、スケッチブックのページが繰られる。新しい紙の上で、また白野の鉛筆
「小鳥さんが心配していましたよ」
「知ってる」
「私も心配しています」
「知ってる。……飲みかけのビールがテーブルの上にあったもの」
ああ、そうでした、と笑う。煎れたての紅茶のカップを少年の前に置いた。自分も向かいの席に座って、ゆっくりと朝の一杯を味わう。
「……で。話しては下さらないんですね?」
「うん。ナイショ」
「最近、『秘密』が増えましたねぇ」
朱里が大仰にため息をつく。それに白野が、フフ…と笑った。
■■4
図書館と隣接した公園には芝生が敷かれ、四季折々の花が植えられ、市民の憩いの場となっている。人の少ない緩く斜面になった芝地に腰を下ろして、朱里は持参したサンドイッチでの簡単な昼食を取っている。C国関連の本の活字を追いながら、今後の方針を考える。
「おい、執事。来てやったぞ」
掛けられた声に顔を上げた。見知った無精髭面が図書館内のカフェテリアのロゴの入ったオレンジ色の紙袋を手にやって来る。
「ああ、ダグラス刑事。よくここがお分かりになりましたね」
「女共が不穏に熱っぽい視線を送っとるその先を見れば、嫌でもお前にたどり着くわい!」
この所の朱里の図書館通いは、ダグラスも当然知っていたし、手弁当なのも小鳥から聞いて知っていた。後は、今日の天気と執事の性格分析である。喫茶室でなく公園だろうと踏んだ。ドンピシャリだ。
「人をわざわざ呼びつけて、何の用だ?」
と訊く。そこへ、噂をすれば何とやら。女の子の一人が彼らの傍にやって来た。すぐ脇を通って水飲み場に行く。彼女が再び通り過ぎるまで、何となく押し黙ってしまう二人である。
「……私の読書行為や歩行活動や咀嚼運動というのは、そんなにもの珍しいものですかね?」
どうも、いつも見張られているようで疲れます。不審者扱いですよ、と苦笑う。
「ストーカー被害で訴える算段に俺を呼んだとか、そんなふざけたこと抜かすなよー」
それに。朱里が「まさか」と言う。
彼女達はさほど実害はありませんから。そのうち飽きてくれますよ。
「うーん、風が気持ち良いなー」
ダグラスは朱里の横にあぐらをかくと、紙袋を開ける。買ったホットドック3個とコーヒーを取り出す。見るからに不味そうなホットドックだ。恐る恐る囓りつく。
「どうだ? 調べ物は進んどるか?」
「それがなかなか。お暇なら刑事も手伝って下さいよ」
こちらは手製のサンドイッチを食べながら、朱里が言う。
「お前に分からん事が俺に分かるかー」
「『コツコツ調べて華麗な推理』は貴方のお家芸でしょう? いつもそう仰っているじゃないですか」
「『コツコツ』の意味が違わぁ」
足で稼ぐ地道な捜査は慣れたものだが、デスクワークはとんと苦手だ。
「……ちょっと、刑事。人のサンドイッチに手を出すのは止めて下さい」
朱里の制止の手を振り切って、奪われたサンドイッチがたった二口で飲み込まれてしまう。口をモグモグさせながらダグラスが手前勝手なゴタクをほざいた。
「だって、このホットドック、すっげぇ不味いんだぞ。だからホレ、残りの2個とそっちの残り、交換しよう」
「嫌ですよ!」
しばらく、食欲を巡る醜い攻防戦がのどかな芝生の上で展開された。結局、恥も外聞も顧みないダグラス側に軍配が上がる。
「……官憲に屈するとは。口惜しい」
「お前、人聞き悪いだろー。等価交換じゃないか」
旨そうに、ハムサンドをパクつく男を睨め付ける。
「等価交換にはちょっと足りませんよ。不足分として、私の四方山
朱里の口の端に浮かんだ薄嗤いに気が付いた。
……あ、俺ってもしかして今、ハメられた……か?
ダグラスがちょっと青くなる。
■
一方。こちらは、木陰に陣取った朱里サマ観賞部隊(仮名)の女の子達だ。お弁当を食べながら、うわさ話に余念がない。
「ねぇねぇ、あの無精髭男、何者なのよぉ?」
「あたし、あたし。さっき、汚したハンカチを洗いに水飲み場に行ったでしょ? さりげなーく横を通ってて聞いちゃったんだ。あの人、『刑事』って呼ばれてたわよ」
「えー、警察!?」
一人の声が高くなった。周りから「シーッ!」とジェスチャー混じりの警告が入る。
「じゃあ、じゃあ、朱里サマも警察関係?」
「あの髪で警察官ってありえなくなーい?」
「警察ってサービス業だっけ?」
「大体、さっきのあの二人、言い争ってる風じゃなかった?」
「そう! ケンカしてた、してた」
「今も睨み合ってる感じ」
彼らが傾斜地に座しているので、女の子達からは詳細が観察出来ないのだ。
「……と、いうことは」
「いうことは?」
「朱里サマのお仕事は、警察とは敵対関係にあるサービス業だということよ!」
ナニやら、あらぬ方向に女の子達の妄想は発展していく。
「フッフッフ……」
「ナニよぉ、アンタのその笑い?」
「わたし、分かってたの。実は」
「何を?」
一斉に一人の女の子にみんなの視線が集中する。
「朱里サマは凄腕のジゴロなのよ! でなきゃ高級ホストっっ!」
「えー、うっそー!」
「いっやーん!」
悲鳴が随所から上がる。
「だって、あのルックスよ? あの髪型に服装よ? それ以外に考えられる?」
「そう言えば、朱里サマって午前中から閉館近くまで、毎日ここに来てるのよねぇ」
「普通の職業だったら、有り得ないわよねぇぇ」
一様に斜面の方を見る。男二人はまだ何事か話をしている。お互いにお互いの話の内容が聞こえないのは不幸中の幸いである。
「……でもさ、ジゴロやホストがどうしてC国の古い伝承とか調べてるワケ?」
「貢がせてる有閑マダムの趣味、だとか?」
「えー、有り得なくなーい?」
「大体、ジゴロって警察の敵なの?」
「どっちかっていうと、ジゴロは『女の敵』だと思うわー」
「……」
女の子達は、お互いに顔を見合わせる。ちょっと嬉しくない結論を導き出してしまったようだ。慌てて方向修正を計る。
「……そう言えば」
さっき、水飲み場に降りていった司書が言った。
「朱里サマって、C国関連の本だけ調べてるんじゃあないみたいよ。この前は昔の新聞記事をそりゃあ熱心に調べてたし」
「あ、私も別のフロアで彼を見たわ」
「どこどこ?」
「えーっとね。『子ども文庫』のコーナー」
えぇー? と声があがる。知的な雰囲気の彼に子ども文庫は似合わない。
「だってだって、ホントだもーん」
口を尖らす女の子に、他の子達が聞き募る。
「じゃあ、何の本見てたのよ?」
「探偵小説。『シャーロック・ホームズの冒険』」
「……」
『ピーターパン』とか、『赤ずきんちゃん』とか言われるよりはマシかしら?
女の子達はそんな事を考えている。
■
「私はこの図書館に通う内に、フーパーという老人と多少親しくなりました」
青空の下。朱里がそう話し始める。信じがたい話でしょうが、とにかく最後まで聞いて下さいよ、と前もって念を押されている。
「この老人、郊外で一人暮らしをしておられたそうですが、足を痛めてしまいましてね、買い物や身の回りを手伝ってくれることを条件に、格安の下宿代で下宿人を募集したそうなんです。最初はなかなかこれといった希望者がなかったそうですが、二ヶ月ほど前にようやく決まりました。男二人です。トンプソン氏とマードック氏と言います」
「ああ、それで?」
ダグラスがサンドイッチを食べながら、先を促す。
「老人曰く、この下宿人達はとても気の良い善人でしてね、老人の世話をあれやこれやと焼いてくれた上、老人が家に閉じこもってばかりいるのは良くない、何処か行きたい所はないか? と、訊いてくれたんだそうですよ」
老人は、元々この図書館で本を読むのが日課でした。足が悪くなってからはそれもままならなくなってしまっていた訳ですが。その話をすると、毎日自分たちが車で送迎してやるから、是非好きなだけ本をお読みなさい、とこう言ってくれたんだそうです。
「良い話じゃないか」
ダグラスが言う。「ええ、全く」と、朱里もそれに同意する。
「ですが、風邪気味で今日は寝ていたいという日の老人にさえ、何これとない理由を付けて図書館通いをさせるとなると、ちょっと妙な気がしてきませんか?」
「あ?」
なんじゃ、そりゃ? とダグラスが訊く。コーヒーで最後のサンドイッチの一かけをゴクンと飲み込んだ。そのままゴクゴクとコーヒーを飲み干す。
「そりゃ、親切の押し売りってもんだろう。それともナニか? その下宿人達には爺さんを家から追い出したい理由でもあるのか?」
ポケットからタバコの箱を取り出した。火を付ける。
「この親切心旺盛な二人組の男達は、それは大したカメラ狂いだそうなんです。老人の家の地下室を暗室代わりに借り切って、始終篭もっているんだそうですよ。……さて、ここまでで、何か思い出したりませんか?」
朱里も自分のタバコに火を付けた。ダグラスに習って、空のコーヒー缶に灰を落とす。
「……おい、ちょっと待て。お前一体ナニが言いたい?」
何事か、思いついたらしいダグラスが、朱里の顔を伺った。朱里はクスクス笑いつつ、「まあ、もうちょっと続きをお聞きなさい」と紫煙をふかす。
公園の鳩が二人の傍に寄ってきた。朱里はその方に袋の中に残ったパンのくずを放ってやる。クックルー、クックルーと鳩がパンくずを啄
「下宿人の二人がね、クーパー老人を迎えに来る時、私は彼らのズボン膝を見ましたよ。だって、気になりますからね。案の定、薄汚れて擦り切れかけているんです。靴にも土汚れが沢山付着してまして。折角綺麗な図書館の床が、彼らの来訪のたびに汚されてしまうんですよねぇ」
全く、毎日掃除する人間の身にもなれ、と言ってやりたくなりました。
朱里がそこで、パンッと手を叩いた。その音に驚いた鳩が羽を広げて舞い上がる。バタバタ……と、飛び立っていく羽音。
ヒラヒラと舞い落ちてくる鳩の羽毛を間に挟んで、男二人がしばし無言のまま見つめ合う。
「……おい、執事」
「どうです? 似ていると思いませんか? あの探偵小説に」
刑事だって子どもの頃、夢中になって読んだでしょう? 何せ今、本職の刑事さんになっていらっしゃるくらいですから。
朱里は揉み消した煙草をコーヒー缶の中に落とす。落としながらクスクス笑う。
「ってよ、お前。そりゃあ幾ら何でも出来すぎだろう? 今の話、まんま、シャーロック・ホームズの『赤毛連盟』じゃないかー!」
ご名答、と朱里が言った。指、ヤケドしますよ、と缶を差し出す。極端に短くなっていたタバコに、ダグラスが「熱ぃっ!」と飛び上がった。
■
「お前、そのクーパーって爺さんの家まで後を尾行
「はい。好奇心を抑えきれず」
追わずにはいられなかった朱里である。
「そ、それで? 銀行はあったのか!?」
ダグラスが勢い込んで訊いてくる。
『赤毛連盟』は、悪い下宿人(原作では奉公人だが)が、民家の地下室から近くの銀行まで地下道を掘り進めていく話である。銀行の地下金庫に納められた大金こそが、彼らの真の目的であった。家主が毎日体よく家から追い払われていた訳は、その時間を利用して、心おきなく犯罪者達が地下道を掘り進める為なのだ。
名探偵シャーロック・ホームズは、その謎を類い希なる推理力によって解き明かし、見事事件を解決する。
朱里は勿体ぶって、二本目のタバコに火を付けた。一息吸ってのんびり吐き出す。ダグラスはそれをジリジリしながら睨んでいる。
「それが。……流石に、現実はそうそう小説のようには進みませんで。老人の家はさびれた通りに建ってましてね。銀行どころか、近くには商店街さえない場所でした」
そんな台詞に、ハッ! とダグラスが笑った。
「そーだろうな。そんな出来すぎた話はな」
「はい。銀行はなかったんですが、代わりの建物があったんです」
「……あ?」
呆けた声が無精髭だらけの口から漏れた。
その夜、朱里はクーパー老人の車を尾行して、彼の家をつきとめた。期待に反してそこは閑散とした場所だった。大金の置かれた銀行や、めぼしい邸宅などある筈もない。それでも、裏通りへと足を進めてみる。細い石畳の通りを挟んで、長く続くコンクリートの塀が高くそびえ建っていた。上部には鉄条網が二重三重に巻かれているのが見て取れる。その塀に沿ってずっと歩くと、やがて固く閉ざされた鉄の門が現われた。門柱にその建物の名前がある。『J刑務所』。そう読めた。
「それで思いだしたんですが、二ヶ月ちょっと前、その刑務所で脱獄未遂事件があったんです。新聞に載っていたんですが、刑事は覚えておられますか?」
「ああ、ウィルキンソンって奴だ」
ウィルキンソンは五年前に三人組の銀行強盗犯の主犯格として逮捕された男である。所持していた拳銃の線条痕が物的証拠となり実刑判決が下ったが、決して仲間の名前は明かさなかった。奪い取った金の在処
「ねぇ、刑事。新聞記事を読んだ時、私はとても奇妙な脱獄囚だと思いました。ウィルキンソンの刑は五年です。既に四年と六ヶ月服役している。あと、たった半年で晴れて自由の身になれる筈の男が、何故、今になって脱獄を企てなければならなかったのでしょうね? 彼が半年を待ちきれなかったその理由は何でしょう?」
「……」
朱里が横に置いていた書類袋をダグラスに渡す。
「図書館の古い新聞記事の中から、私に出来うる限りの情報を集めてみました。どうぞ、刑事に差し上げます」
■
これはあくまでも仮説である。仮説であるが、恐らく間違ってはいないと思う。
クーパー老人の気の良い下宿人・トンプソンとマードックは、五年前、ウィルキンソンと共に銀行を襲った犯人一味だ。彼らはずっと息をひそめ、ボスの帰りを待っていた。何故なら、主犯のウィルキンソンが強奪した金を何処かに隠し、不幸にしてその直後、警察に捕まってしまったからだ。二人は当然金の在処を知らされていない。刑期を終えたウィルキンソンが戻ってきたら、密かに彼らは連絡を取り、金を分け合うつもりだった。
ところが、ここに来て思わぬ誤算が生じた。ウィルキンソンの釈放まで決して待つことの出来ない、不測の事態が起こったのだ。ウィルキンソンは慌てて脱獄を企てるが、失敗に終わる。そして、ウィルキンソンの脱獄未遂事件をニュースで知った手下二人も、何か重大な問題が起ころうとしているらしいことに気が付いた。中から出られないのなら外から助けよう。トンプソンとマードックは小説を模して、ボス救出の為の地下道を掘る。
ダグラスが、朱里から受け取った新聞のコピーを読みながら尋ねる。
「その『不測の事態』ってなぁ、何だと思う?」
「さあ? 新聞記事から得られる資料だけでは流石にね」
ただ、私はこう思います。ウィルキンソンが隠した大金の在処。多分、何処かのビルか何かでしょうが、それが近日取り壊されるという新聞記事を檻の中のウィルキンソンは読んだんですよ。猶予は半年もないと知ったんです。
「……はぁぁー」
と、ダグラスがため息をつく。
「幾ら、お前の話でも、流石にコレは信じがたいぞ」
「ええ。私自身、そう思います。笑い話みたいですよね」
ですが、理性を捨てて、さっさと信じてしまって下さい。まだまだトンネル掘りには時間が掛かるだろうとタカを括っていたのですが、どうやらそうでもなさそうなんです。手下二名は私が思っていたよりもずっと有能らしいです。
「何だよ、トンネルが完成したのか? お前、見たんか?」
「まさか」
朱里がクスリと笑う。
「今朝もいつも通りにトンプソンが、フーパー老人を送ってきました。その帰りにね、トンプソンは図書館の司書の女の子とぶつかったんです」
それはもう、えらい剣幕で女の子を怒鳴りつけていましたよ。これまでは始終にこにこ、大した善人ぶりでしたのにね。
「つまり、彼らはもう『良い人』を演じる必要がなくなったんです。おそらく、計画決行は今夜です」
■
ダグラスと公園で別れた朱里は、そのまま真っ直ぐ館に戻った。まだ陽の高い時間に帰るのは久しぶりである。
車から降りると、その音に気づいたのか、小鳥が玄関口から駆け出してくる。
「朱里さん〜〜〜っっ」
「どうしました?」
小鳥は何故か涙目だ。今度は一体何事だ?
「玉子の数が足りないの!」
「……はい?」
「冷蔵庫の中の生玉子が、いつの間にか二個足りないの〜」
きっと、真夜中に白野様が食べちゃったのよぉ。やっぱりヘビに取り憑かれているのよぉ。ヘビは生玉子を食べるのよぉぉ〜っっ
「……」
凄い、凄すぎる、と思う。
ついさっき、ダグラス相手に『普通に考えたら、到底有りそうにない話』を語ってきた朱里だったが、小鳥にはとても及ばない。
「どうしよう〜、白野様にウロコが生えたら、わたしショック死しちゃうよぉ〜」
私の方がショック死寸前ですよ、とか思う。何とか小鳥を落ち着かせ、白野様の様子を見てきますから、と納得させる。
「お願いね。ちゃんと加持祈祷して悪霊調伏
「はいはい……」
小鳥さんの私に対する認識は一体全体何なんだろう? 既に『執事』も『便利屋』も通り越して、人外の生物に設定されてしまっている気がする。……ああ、気が滅入る。
朱里は重い足取りで階段を登っていく。目指すのは白野のアトリエだった。
「……白野様?」
アトリエに入ると、男は主の姿を探した。
少年はソファーの上。数冊のスケッチブックを抱え込むようにして、ぐっすり眠り込んでいる。
TRRR……。TRRR……。
ふいに電話のベルが鳴った。出ると、セント伯爵である。セント老人の声は常になく狼狽した様子だった。
そして。朱里はまた一つ、『到底有りそうにない話』を耳にする。
■■5
TVは『前代未聞の脱獄計画』についての特集番組を流している。
銀行強盗三人組は揃ってお縄となり、その自供から奪われたまま行方不明だった金も出てきた。区画整備事業の一環で近く取り壊しの予定だった廃ビルから発見されたそうだ。ほぼ、朱里の想像した通りの展開である。
トンプソンとマードックが護送されていく様子が画面に映る。
それを眺めつつ朱里は、内心小気味よい爽快感を味わっている。
「……ずっと、安全運転に徹していれば良かったのにね」 と、小さく呟く。
朱里が図書館通いを始めた、その初日。
図書館の敷地内で、思い切り朱里に水溜まりの水を浴びせてくれた車があった。それがフーパー老人をいつも送迎している下宿人の車だったと知った時。
これが、朱里が疑惑を抱いたそもそもの発端だった。老人の前では、善良で温厚な仮面を被っていた下宿人達は、本当は老人を送迎する時間すら惜しんでいたのだ。老人を図書館に届けると、大急ぎで飛んで帰る。その時の無謀な運転ぶりが、老人の話す下宿人達の様子と違いすぎていた。気になった。
というか。有り体に言えば、これはちょっとした仕返しができそうな気配だぞ、と朱里は思ったのである。彼らは不審人物だった。その正体を暴いてやれば、被った泥水の意趣返しができる。……まさか、ここまで大きな事件に発展するとは流石に予想外だったが、とにかく、男達は逮捕され、罰せられる。朱里は大いに溜飲を下げたのである。
■
「朱里は図書館で随分楽しそうなコトやってたんだね。僕も尾行とかしてみたかったなぁ」
ソファーの上で膝を組んだ白野が、いかにも残念そうな口調で不満を漏らす。朱里がそれをたしなめた。
「白野様はこのところ、ずっと寝ているか、絵を描いているかだったでしょう。図書館にお誘いしたところで、来て下さらなかったと思いますが?」
よって、私に文句をおっしゃられても、困ります。
「大体な、坊や。普通、一般人はそうそう事件を嗅ぎつけたり、尾行なんざしないんだ。くれぐれも真似するなよ。危険な目にあっても知らんぞ」
一緒にTVを眺めていたダグラスも、そう釘を刺す。
「……」
白野が口唇を尖らせた。
その手にスケッチブックとペンは握られていない。白野はある日を境にパタリとヘビの絵を描かなくなった。四六時中ひどく眠たげな様子も見せなくなった。今、のほほんとTVの画面を眺めている目はどこか眠たそうに見えはするが……これは元からそうである。
小鳥は、白野様に取り憑いていたヘビが調伏された、と大喜びだったし、ダグラスも手柄を一つ増やした。唯一の問題は、セント伯爵邸の美しい紅茶器から鳥の絵が突如消え失せたという怪奇現象であったが、そのお陰で、朱里はC国の鳥についてこれ以上調べる必要がなくなったので、良しとしておこうと思う。全てはハッピーエンドである。
TVは渦中の人、フーパー老人を映している。
老人は今後、週に二回、ボランティアの人が図書館まで送迎をしてくれることになったらしい。図書館に来れる時間は減ってしまうが、家の地下に大穴を開けられるよりはマシだろう。
■
「ああ、そうでした」
TVがCMになったところで、朱里がダグラスに訊く。
「つかぬ事を伺いますが、刑事、この間いらした時に玉子をお使いになりませんでしたか?」
「あー、すまん。夜中に腹が減ったから、勝手に茹でて喰っちまった」
「……」
悪びれもせず、ワハハと笑うダグラスが、ついつい憎らしくなってくる。その所為で要らぬ苦労をさせられた。朱里に無言で睨まれて、ダグラスの顔が鼻白む。
「何だよ、沢山あったじゃないか。玉子くらいでケチケチすんなよ」
「いえ、私は一向に構わないのですが、……小鳥さんが泣いていたので」
「あ? 何で玉子の二個で小鳥が泣くんだ?」
ポカンと口を開けた男の顔が面白いので、こう言ってみる。
「そうですね。ちょっと私の口からは説明が難しいんですが……。大変デリケートな問題です。小鳥さんが買い物から戻ったら、ちゃんと謝っておいて下さいね」
「お、おう……」
ダグラスが困惑顔のまま、何度も頷く。
たまには刑事にも小鳥さんの超論理思考の犠牲になって貰おう。朱里は心中ほくそ笑む。
この執事、実に根に持つタイプの男なのである。クワバラ、クワバラ。
■■エピローグ
市立図書館、給湯室。
司書の女の子達が、ため息と共にこんな会話を交わしている。
「朱里サマ、やっぱり、今日も来なかったわね」
「もう、会えないのかしら?」
ああ、職場の潤いがー、楽しみがー。肩を抱き合ってよよと泣く。
結局、あの背高のっぽのハンサムは一体何者だったのだろう? 警察関係者だったのか、それともジゴロだったのか? 彼は突然この図書館に来なくなり、そして謎だけが残ってしまった。ああ、満たされぬこの好奇心。
そこに、別の女の子が一人、息せき切って駆け込んできた。
「ちょっと! 朱里サマが今、カフェテリアに来てるわよ!」
「ええぇぇぇ〜〜〜!」
女の子達は駆け出していく。壁に貼られた『館内では騒がない! 走らない!』の文字がムナシイ。
「どこよ、どこどこ?」
「あ、居た。あそこ!」
黒服長身の男はすぐ見つかった。カフェテリアのオレンジ色の袋を手に、公園の方へ歩いていく。
■
「はい、どうぞ。白野様。ご所望のホットドックです」
「ありがと、朱里」
先に、公園の芝生に座って、のんびりと鳩など眺めていた少年が、礼を言って男の手からから紙袋を受け取る。朱里も芝生に腰を下ろした。嬉しそうに袋の中に手を入れる少年を見るその顔は、かなり呆れ気味だ。
スケッチブックの予備がもうなくなった、という白野を連れて、今日は画材屋まで車を走らせた朱里だった。折角外出したのですから、帰りは何処かに足を伸ばしますか? 行きたいところがありますか? と、常日頃から館の中に引き籠もり気味の主に問いかけると、
「じゃあ、図書館に寄ってくれない?」
などと言う。
「はあ、それは構いませんが。何か調べ物ですか?」
その予想外の返答に疑問を持って聞き返す。
「ううん。カフェテリアで売られてるホットドックが食べたくって」
「……は?」
更に予想外である。面食らう。
「ダグラス刑事が言ってたんだよね。『あそこのホットドックは殺人的に超マズイ』って」
「……何故、そんなモノを召し上がってみたいんです?」
「だって、『殺人的』だよ? 『超絶に美味しくない』んだよ? 食べてみたくなるじゃない」
「……」
結局、「海よりも山よりも川よりも谷よりも、絶対ホットドックの方がいい!」 と言われて、連れてきてしまったが、早速、目聡い図書司書の女の子達に見つかってしまった。どうやら、また遠巻きに観察されているようだ。今日、朱里の隣には白野が居る。一体、女の子達の頭の中では、この新情報がどのような味付けで朱里の人物像に加味されてしまうのか……。かなりコワイ。頭が痛む。
■
「ねぇ、朱里」
白野が不思議そうに訊いてくる。
「何で、あそこの女の人達、こっちを見て騒いでるの?」
ムグムグとパンを頬張ったまま、女の子達の方をアゴで示す。ちょっとお行儀が悪い。
「さあ? 男には計り知れない、女性特有の深遠なる理由が隠されているらしいですよ」
投げやり気味にそう返事をすると、
「ああ、そう言えば小鳥ちゃんも、時々あんな顔して僕らのコト見てるもんね」
大して頓着した風もなく、納得顔で「うんうん」と頷く。コーラをストローで吸い上げる。
「……」
本当に分かっているのだろうか? 分かっているなら、この無頓着は心配だし、分かっていないなら、尚更だ。
ため息をつきつつ、朱里の親指が白野の口唇の端を軽く擦った。
「……?」
「ケチャップです」
指に付いた赤い色を、白野の目の前でかざしてみせる。そして、そのまま普段のクセで、つい、その指先を舐め取った。途端に女の子達の「キャー」という嬌声が響いてくる。しまった。また彼女達に格好のネタを提供してしまったようだ。ああ、気が滅入る。
「ねぇ?」
白野が、また不思議そうに訊いてくる。
「何で、あの女の人達、今叫んだの?」
「……余り、答えたくありません」
「ふぅん。じゃあイイや」
別に良くはないんですがね、と思う。思うが言及したくない。とにかく、当面ほとぼりが冷めるまで、この図書館を利用するのは止めにしよう。朱里は固く心に誓う。
■
犬を連れた老婦人が二人の前を通った。犬はずっと白野を見ている。飼い主に引き綱を引っぱられて仕方なげに離れていくが、少年が食べているホットドックが気になって仕方ないらしい。
去っていく犬を横目に見ながら、モグモグと口を動かす少年に。これもついつい、いつものクセで尋ねてしまう。
「美味しいですか?」
それに。白野が思い切り眉間に皺を寄せてみせる。『何言ってるの? 信じられない!』という顔だ。
おっと、しまった。しくじった。
「……愚問でしたね。言い直します」
改めて、もう一度問いかける。
「白野様、どうです? 不味いですか?」
口の中のホットドックをコーラで喉の奥に流し込むと、白野少年は朱里に向かってにっこり笑う。蒼い双眸が嬉しげに輝く。
「うん! もンのっすご〜〜〜く、超マズい!」
「……」
その言葉とは裏腹に、とても満足そうな顔。男は思わず天を仰ぐ。
紅茶器の鳥の一件といい、ヘビの絵といい、これといい。
「……白野様」
「ん、なに?」
白野が軽く小首を傾げる。その、のほほんとした表情が、無念ながら全く読めない。
「……結局の所、貴方様が一番、『謎』ですよ」
そう断言してやると、朱里はそのままパタンと芝草の上に寝ころんだ。空は青く、ぽっかりと白い雲が浮かんでいる。深く深呼吸して目を閉じた。
白野はその横で、滅多に口に出来ない激マズのホットドックを、心ゆくまで味わっている。
■■後書き
11話『壺の鳥』で、白野がヘビの絵を描きまくっている頃、朱里はナニしてたのか? というお話しです。
『壺の鳥』がある種淡々とした話だったので、こっちは「おちゃらけ」に徹してみました。白野が幻想的な夢の世界を彷徨っている頃、朱里は普段にも増して、とても現実的に生きておった模様です。毎度お疲れさんな奴だなぁ。
かなり脳みそ使った割には「おちゃらけてる」ので、なんだかなー、、、な感じ。ちと口惜しい。そのうち、しんみりした話も、また書きたいと思います。
作中に登場する『赤毛連盟』はWEB上でも読めます。
皆さんご存知の話だとは思いますが、これを機会に再読されては如何でしょう? 私はホームズ作品の中で、これが最高傑作だ、と思っておりヤす。
シャーロック・ホームズの冒険 『赤毛連盟』 (マルチメディア対訳版)
よろしければ、ご感想などお寄せ下さい。
お気に召したシーン・台詞なども教えて頂けると喜びます。
宇苅つい拝
タイトル写真素材:【写真素材 ねじ式】
ツイート よければTweetもしてやってね |